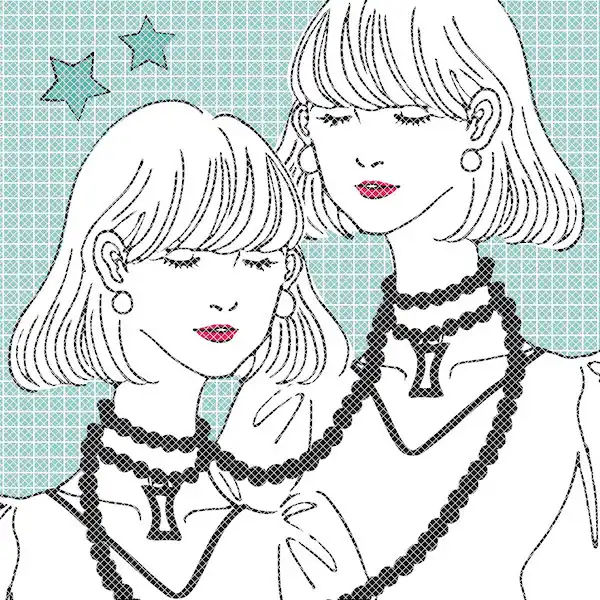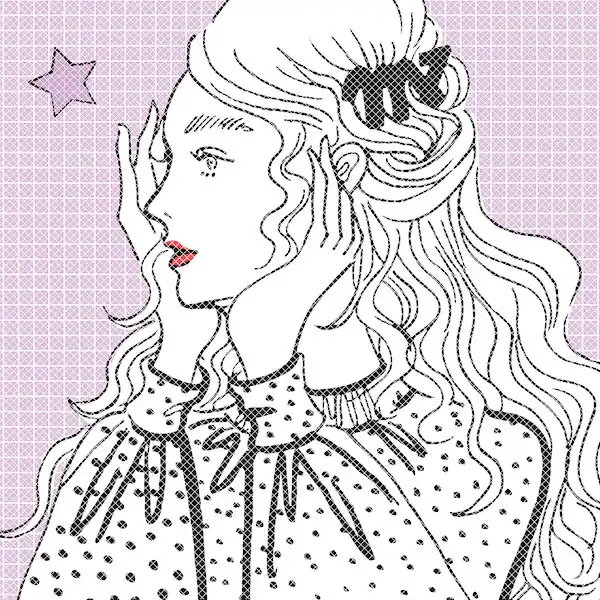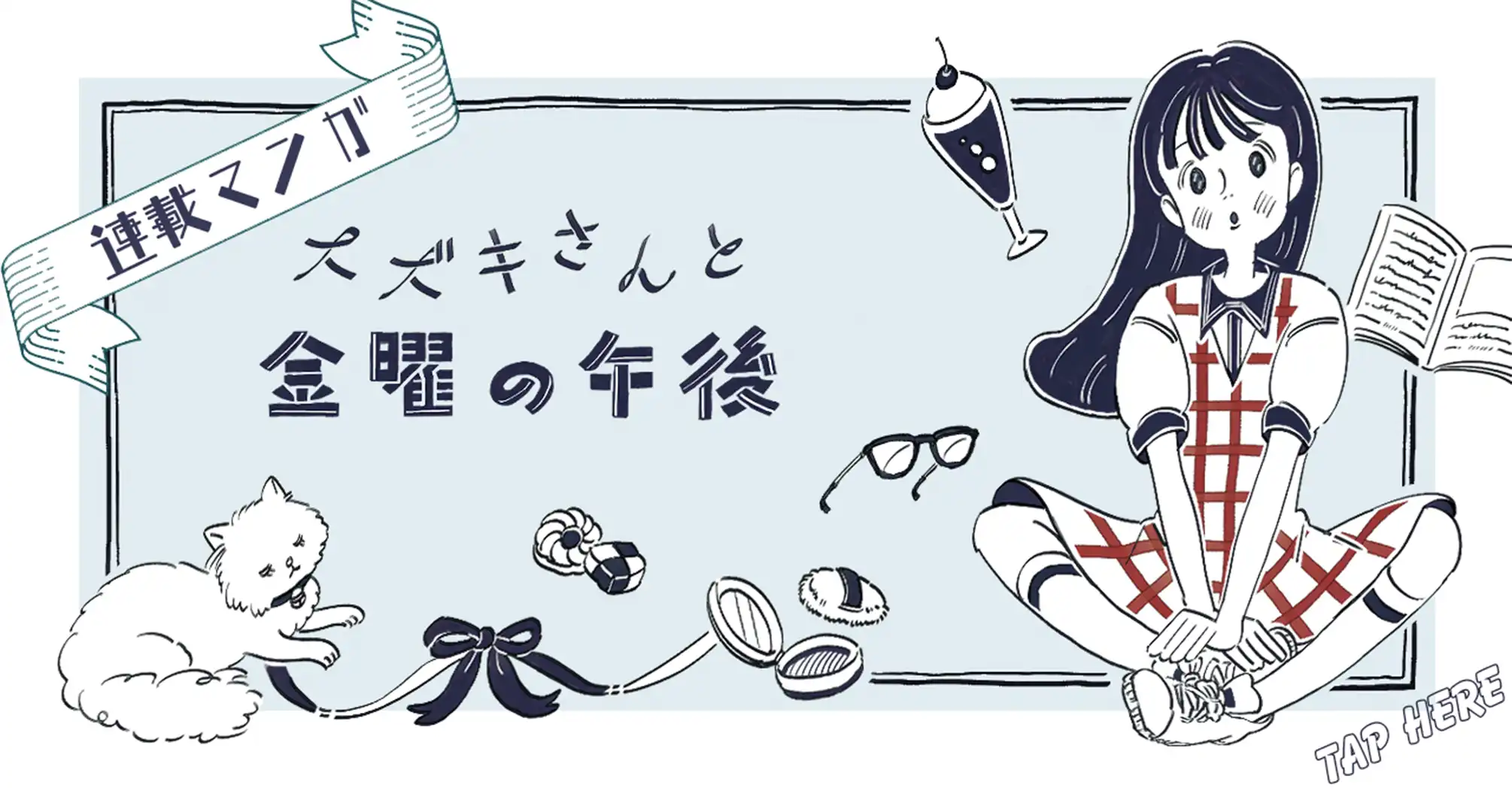いて座
器に徹する
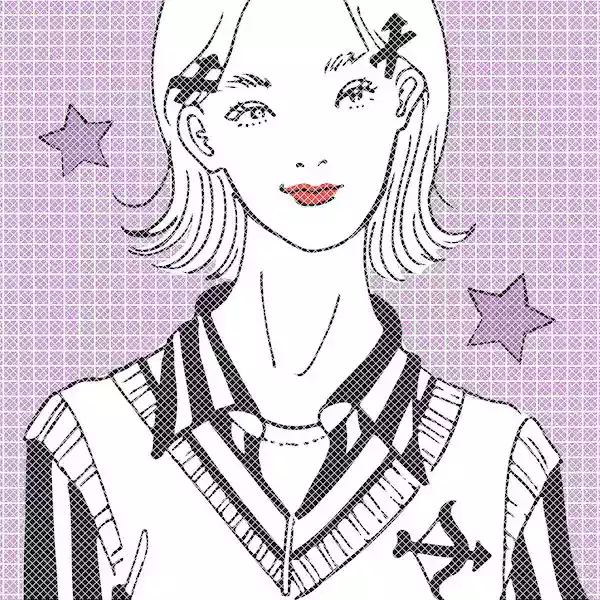
風のように言葉が通過していくということ
今週のいて座は、過去や死者を宿す器としての喉元のごとし。あるいは、慄(おのの)きつつもほっとするような感覚を通じて言葉を紡いでいこうとするような星回り。
困難な状況にある人にただ単に「がんばれ」と言い続けてしまうのは、言葉をかける側が想像力を失い、本来かけるべき言葉を見失っているからですが、では、そんな時私たちは一体どうすればいいのか。例えば、近代日本思想を専門とする中島岳志は、『現代の超克―本当の「読む」を取り戻す―』の中で、ヒンディー語の与格構文という構文に言及しつつ次のように述べています。
ヒンディー語では、「私は、ヒンディー語を話すことができる」は、「私にヒンディー語がやってきてとどまっている」という言い方をするのです。「私」という主体が言語というものを能力によってマスターし、それによって私が主体的に言語を話しているのではないのです。「私」という器に言葉がやってきて私にとどまっている、という言い方をヒンディー語ではします。では、言葉はどこからやってくるのか。それは、過去からであり、死者からです。過去や死者からやってきて、私にとどまり、そして私の中を風のように通過してこの口を伝って言葉が出てくる。そうとしか思えない、ということがヒンディー語の中に与格構文として組み込まれています。
中島は、何かを話しているときに慄くときの感覚について「喉元に死者がいる」という言い方もしているのですが、慄くとともに「少しほっとする」のだとも言います。それは、自分がひとり単独の存在ではなく、死者や過去と言葉を通じてつながり、ともに生きていることを感じられたからでしょう。
28日にいて座から数えて「神殿」を意味する9番目のしし座で上弦の月を迎えていく今週のあなたもまた、ふとしたときの言葉のあり方を通じて、そうした「喉元に死者がいる」ということや、死者が紡いだ言葉を宿す器になるということがいかに可能なのか、ということがテーマとなっていくでしょう。
<私>の叫び
例えば、カリブ海諸国出身の詩人デレック・ウォルコットに『名前』という詩があります。そこでは、名もなき島の子として、海とともに始まり、海上を飛翔しつつ鋭く魚を捕らえる<私>がこの世界に生まれ出ようとしているまさにその瞬間が歌われています。
私という種族は海の始まりとともにはじまった
そこには名前もなく、地平線もなかった
ただ舌の裏側の小さな小石だけがあり
星に記された異なった位置だけがあった
(……)
岩影から海の鷲が叫ぶ
あのミサゴの叫びのようにして
私の種族は始まったのだ
あの恐ろしい母音とともに
あのI(わたし)という!
(『デレック・ウォルコット詩集』)
ここでは自分という存在がこの世に生じてから、これまでの軌跡がそのまま詩、すなわち「私のなかを風のように通りすぎていく言葉」へと昇華されています。
その意味で、詠うこともまた、死者との交錯であり、何よりそれは生者にとって生き延びるための原動力となっていくのです。今週のいて座もまた、そんなことを頭の隅に置いて過ごしてみるといいでしょう。
いて座の今週のキーワード
恐ろしい母音とともに