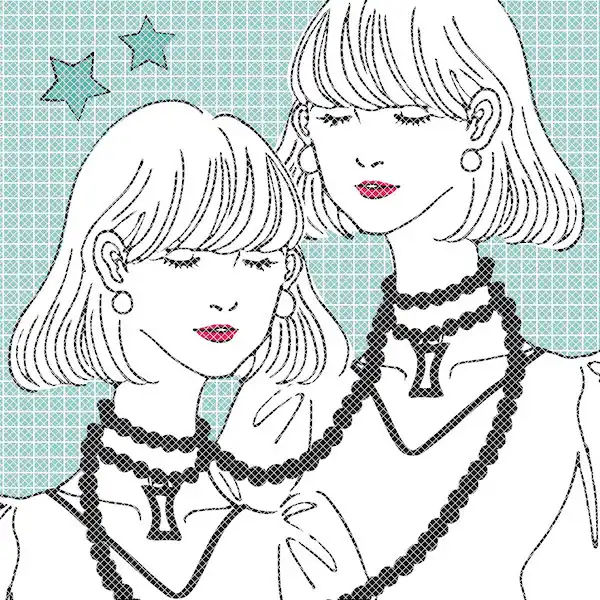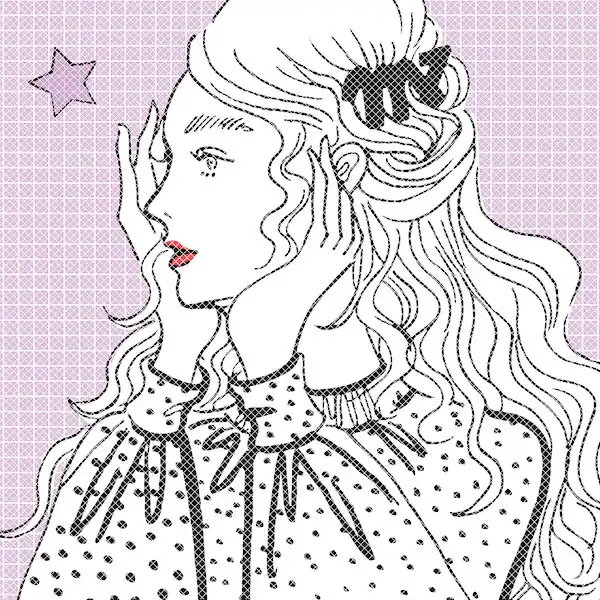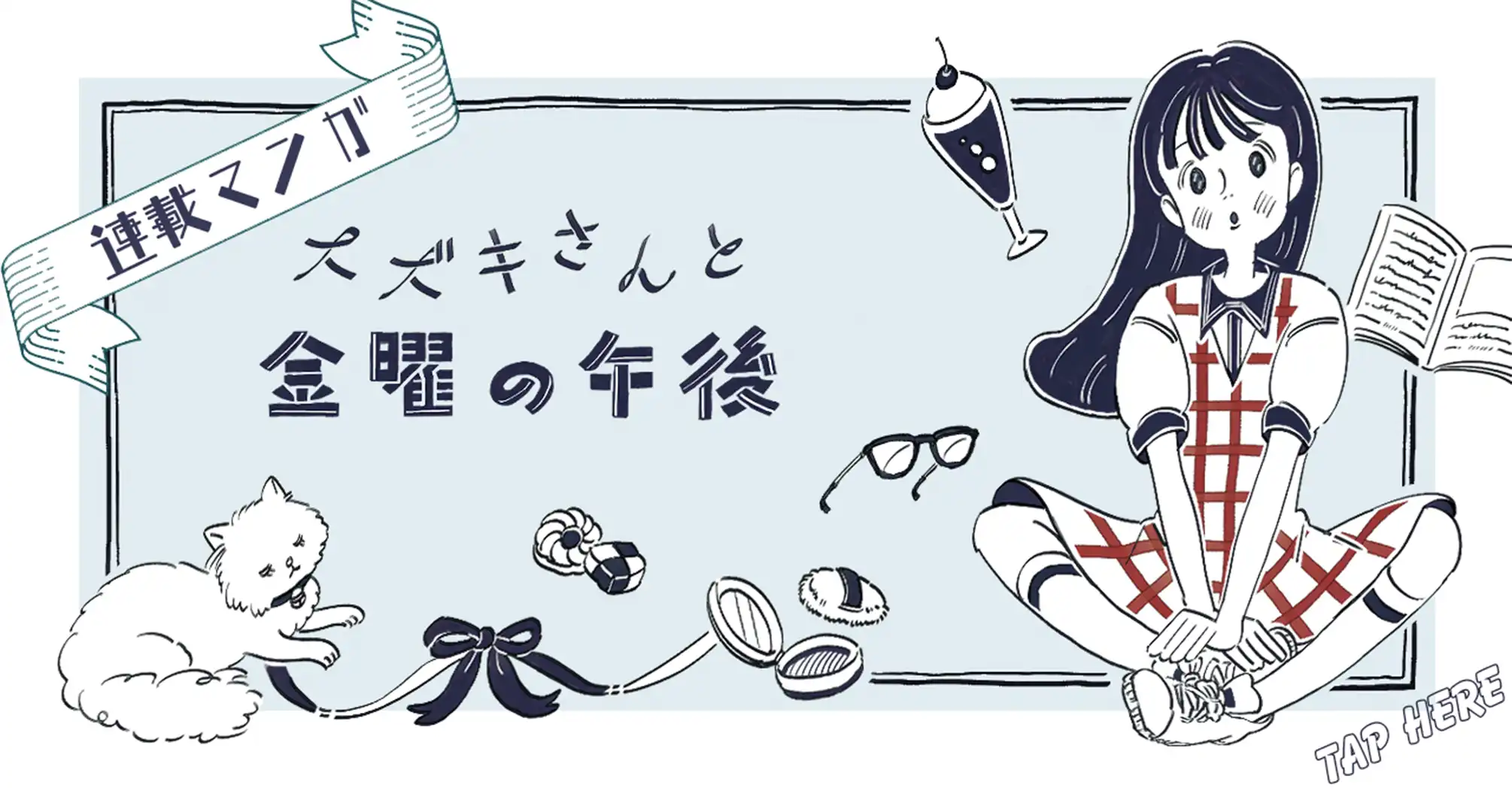いて座
結び目としてのわたし
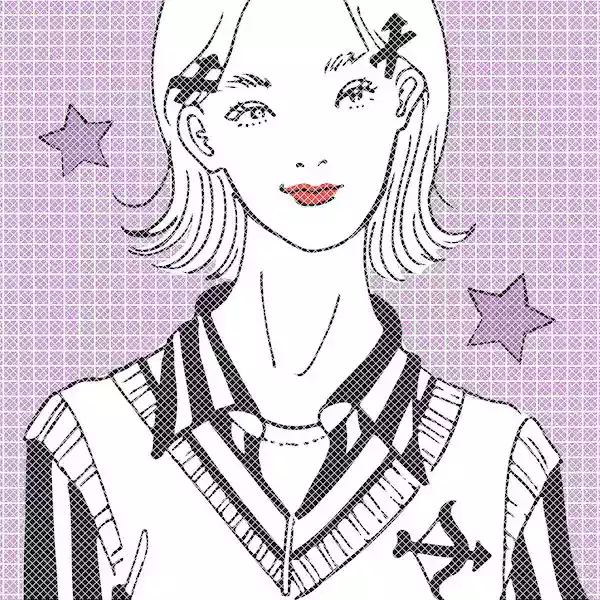
遠い糸を受け取る
今週のいて座は、鎌倉時代の僧・忍性(にんしょう)の或る弟子のごとし。あるいは、個人の一生を超えたスケールで存在する働きかけにアクセスしていくような星回り。
寛元の初め(1243)に畿内の癩者(らいしゃ)つまりハンセン病患者1万人以上を集めて食べ物を施行したとされる忍性には、中でもとても印象的なエピソードが残されています。
…奈良坂に癩者あり。手足よじれて物乞いするに難し。故をもって数日、喰わずしてあり。時に忍性、西大寺にあり。これを憐れみて暁に奈良坂の宅にいたり、癩を負いて市中に置き、ゆうべに置いてその癩者の舎に帰る。かくの如きは数年、日を隔ててゆき、風雨寒暑といえども欠かさず。癩者、死に臨みて曰く。我、必ずやまたこの世に生まれ変わり、師(忍性)の役(手伝い)として師の徳に報いんと。しこうして、顔面に一瘡(一つの傷)を留め、証拠となすのみ……。(『元享釈書』)
つまり、身動きできず、物乞いにも出かけられない癩者を背負って坂と市中をくる日もくる日も往復したのだと言うのです。「一瘡」を顔に留めることを誓って去っていったその癩者は、果たして蘇ったのか…?蘇ったのだ。
…はたして、忍性の弟子の中に、顔に瘡の者あり。給仕役をよくす。人呼んで、癩の後身たりと……(同上)
もちろん、こうした伝承を眉唾ものと決めこんで一掃するのは簡単でしょう。けれど、他の非人(被差別民)たちがこの話をまことしやかに噂しただろうこと、そして中にはそこに何か信じられるものを見出した者がいただろうことは確かなように思えるのです。
12日にいて座から数えて「先祖の記憶」を意味する12番目のさそり座に火星が入っていく今週のあなたもまた、そんな紙一重のところで信じられるような奇跡や足跡のなかに、自身の歩みを後押ししてくれる超自然的なはからいを感じ取っていくことができるかも知れません。
宇宙のように複数であれ
フェルナンド・ペソアという詩人は、1888年にポルトガルで生まれ、8歳のとき母親と義父に連れられて南アフリカに移住し、そこでイギリス風の教育を受けて英語でものを書き、成人後にひとりでリスボンに帰って(今でいう帰国子女)、商社で働いて生計を立てつつポルトガル語で詩作を続け、47歳で没したという。
この経歴だけでも幾重もの「仕掛け」のようなものを感じさせますが、さらに彼は3人もの詩人を「発明」して、それぞれに丹念なライフヒストリーを与え、それぞれの名で詩集を出しています(もちろん、「自分本人」が書いた詩集とは別に)。そしてその中のひとりが書いた詩には、次のような一節があります。
詩人はふりをするものだ/そのふりは完璧すぎて/ほんとうに感じている/苦痛のふりまでしてしまう(詩と詩人について)
今週のいて座もまた、どこかでぺソアのように、巧妙な「ふり」を通じて硬直しがちなリアリティを複数に分散してみるといいでしょう。
いて座の今週のキーワード
「私はもはや自分のものではない。私は、打ち棄てられた博物館に保存された私の断片なのだ」(ペソア)