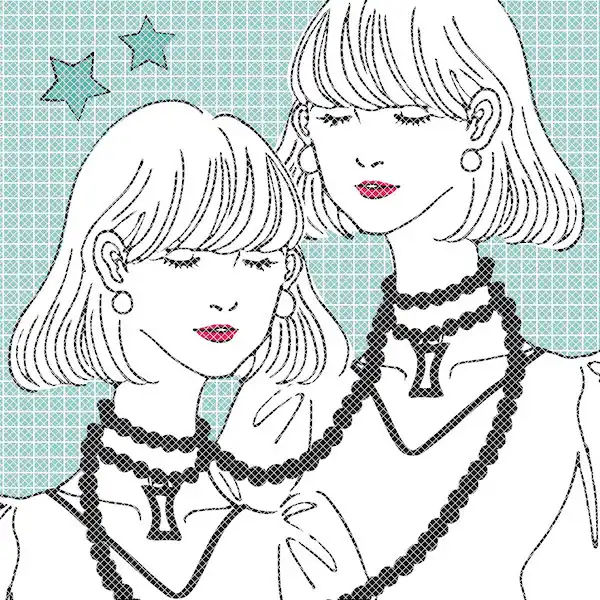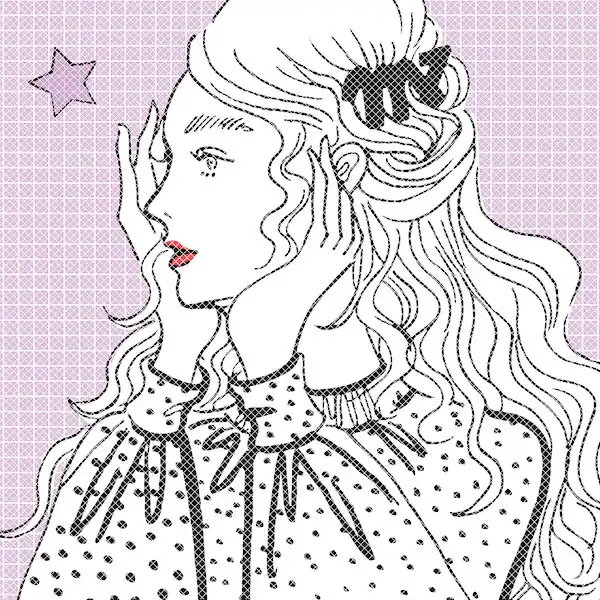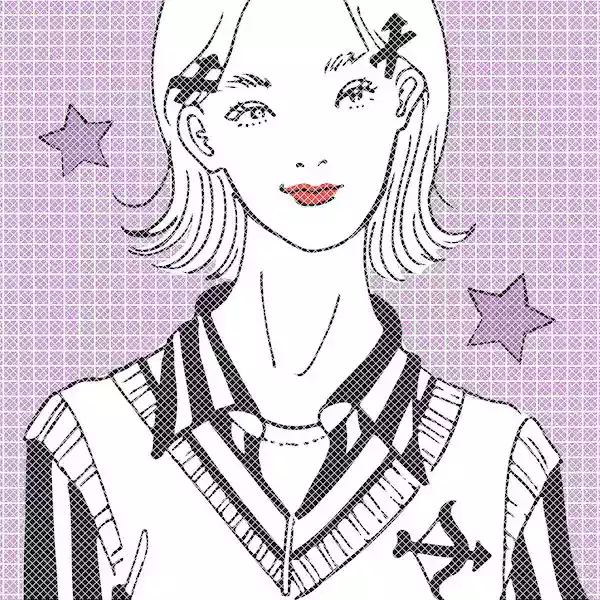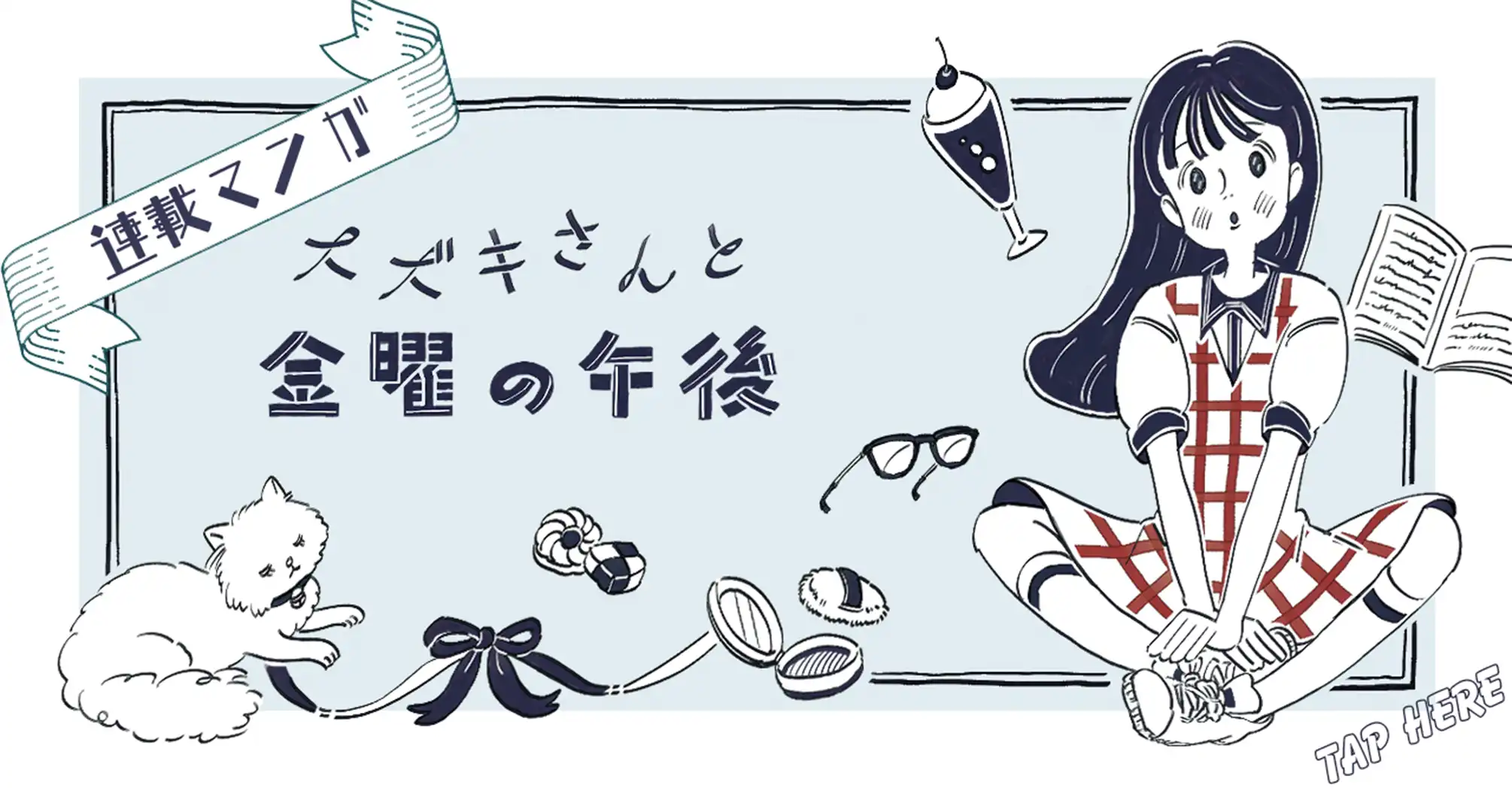うお座
まなざしを掘り起こす

何らかの仕方で表現すること
今週のうお座は、村上春樹の「ニューヨーク炭鉱の悲劇」という短編小説のワンシーンのごとし。あるいは、不可視の領域に耳をすませていこうとするような星回り。
1981年3月に『BRUTUS』誌に発表されたこの小説は、話者である28歳の「僕」の回想という形式をとりつつも、ビージーズの「New York Mining Disaster 1941」という曲の歌詞に着想を得たのだろう、落盤事故にあい生き埋めになった鉱夫たちの場面が出てきます。
空気を節約するためにカンテラが吹き消され、あたりは漆黒の闇に覆われた。誰も口を開かなかった。五秒おきに天井から落ちてくる水滴の音だけが闇のなかに響いていた。
「みんな、なるべく息をするんじゃない。残りの空気が少ないんだ」
年嵩の坑夫がそう言った。ひっそりとした声だったが、それでも天井の岩盤が微かに軋んだ音を立てた。坑夫たちは闇のなかで身を寄せ合い、耳を澄ませ、ただひとつの音が聞こえてくるのを待っていた。つるはしの音、生命の音だ。
彼らはもう何時間もそのように待ち続けていた。闇が少しずつ現実を溶解させていった。何もかもがずっと昔に、どこか遠い世界で起こったことであるように思えた。あるいは何もかもがずっと先に、どこか遠い世界で起こりそうなことであるように思えた。
みんな、なるべく息をするんじゃない。残りの空気が少ないんだ。
外ではもちろん人びとは穴を掘り続けている。まるで映画の一場面のように。
このシーンは、当時日本社会に静かに進行していた見過ごしてはいけない事態の村上なりの比喩なのかも知れません。
そして、9月7日にうお座から数えて「訴えるべきこと」を意味する7番目のおとめ座で新月を迎えていく今週のあなたもまた、結局、自分が社会に異議を申し立てたいこととは何なのかを先鋭化していくことがテーマとなっていくでしょう。
不可視の領域へのまなざし
この作品の解釈をめぐって、山根由美恵は『村上春樹「ニューヨーク炭鉱の悲劇」<切断>という方法』という論文で、「私たちの身近なところにいつも潜み、突然その姿をあらわす」死の「危うい感覚」が、挿話を通して描かれているのだと指摘しています。
一方、加藤典洋は『村上春樹の短編を英語で読む』のなかで、作品を通じて村上は法律上の殺人でも道義上の殺人でもないそこらへんにいくらでも転がっている「死」への思い、関係が描かれているのだ述べます。そして、社会から隔てられた「戦場」という不可視の「坑内」に「生き埋め」になった人びと=ヴェトナム戦争の出征兵士の動向に耳を澄ませているのであり、村上はこれを1977年の自分を起点に、日本社会に静かに進行していた「戦争」ないしそれに類するものとして、学生運動の衰退の過程で引き起こされていったセクト間、セクト内の「内ゲバ」に耳をすませていたことがうかがえます(村上の出身大学である早稲田大学は内ゲバの当事者セクトである革マル派の牙城の一つでした)。
今週のうお座もまた、そうした今まさに自分と隣りあわせの危機や危うさに対し、自分なりの主張や論点をできるだけ明確にしていきたいところです。
うお座の今週のキーワード
生き埋めにされた声に耳をすませていく