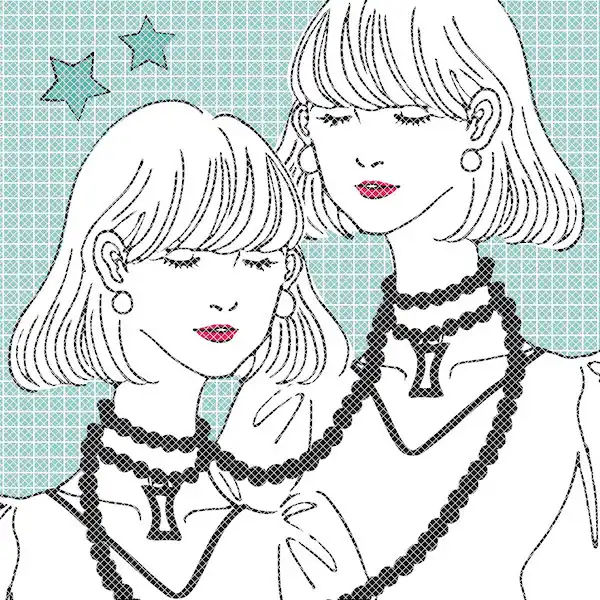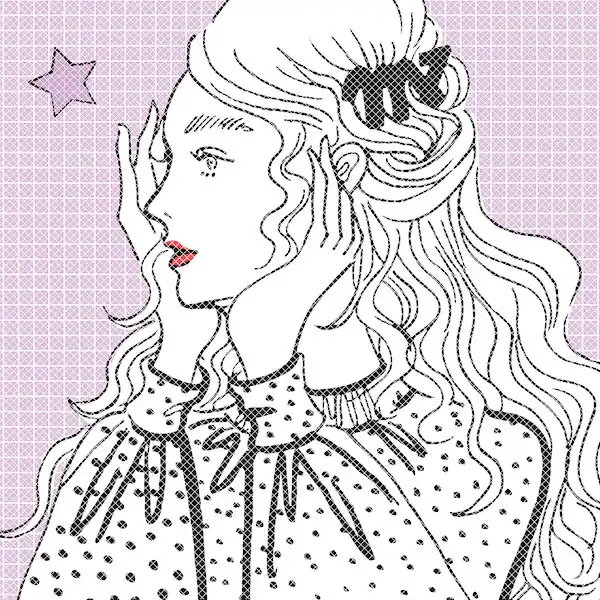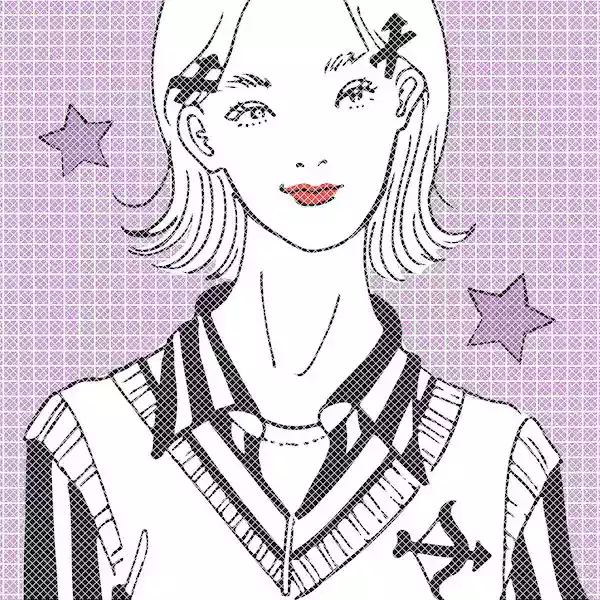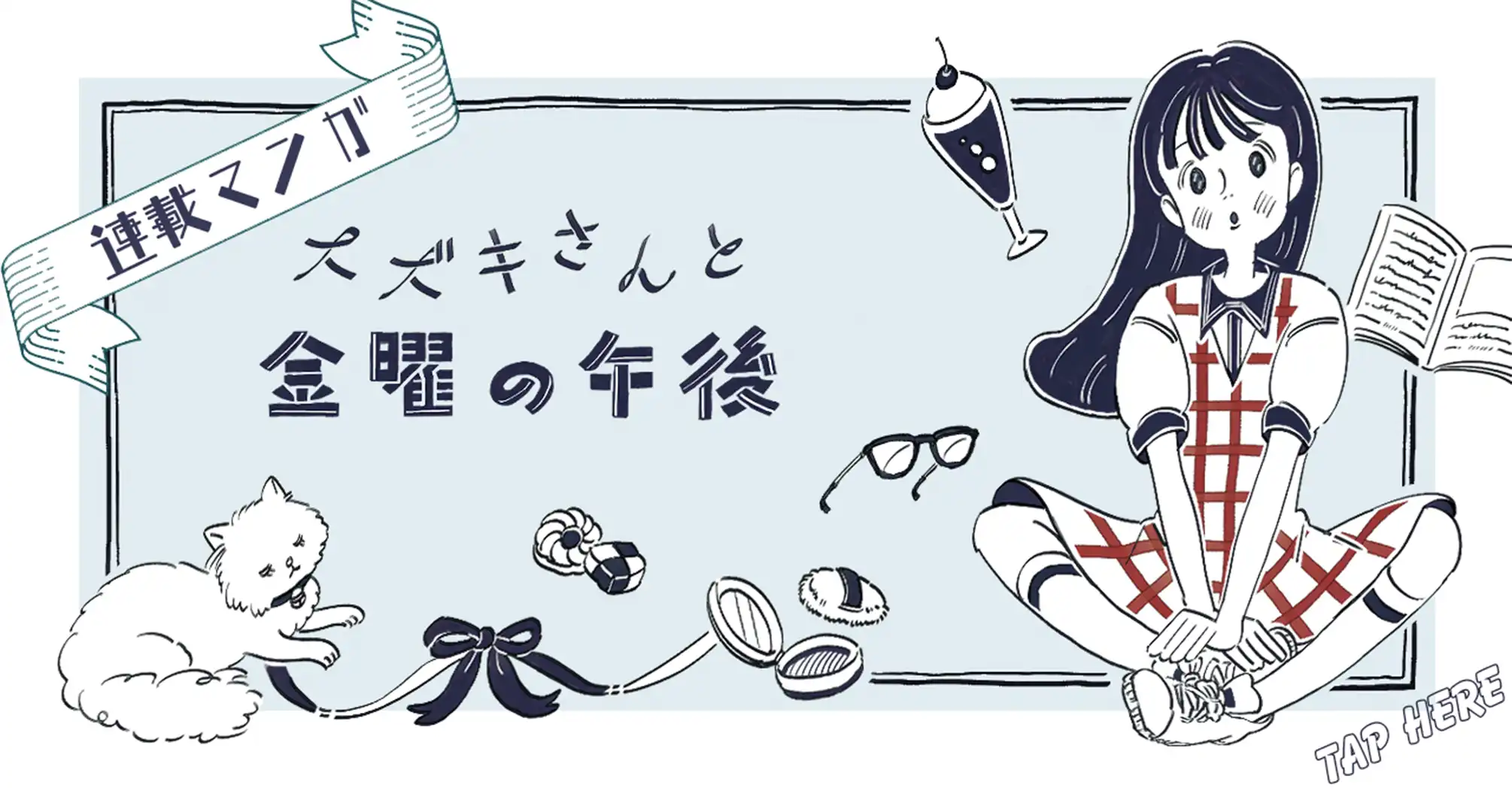しし座
光と闇の果てしないバトル

小さな燈火に向き合う時間
今週のしし座は、「このランプ小さけれどもの想はすよ」(冨澤赤黄男)という句のごとし。あるいは、不安に押し潰されそうな時にこそ、火を灯していこうとするような星回り。
掲句は、作者が戦地から軍事郵便で送った連作の一つで、1939年1月号の「旗艦」に掲載されたもの。
拾ったランプを灯して、塹壕で不安な一夜を過ごしながら、遠い地にある娘のことを思い出していたのかも知れない。この句は一兵士の心情吐露でありながらも、そこには確かな普遍性が兆している。
ほんのわずかな明かりであれ、真っ暗闇と、ほとんど真っ暗とではまったく異なるという点では、1930年代の戦地も2010年代の現代社会もそう変わらないはずだ。
たとえコンクリートの壁に囲まれ、一見すれば何不自由のない状態にあろうと、そうした「小さなランプ」に人は救われる時があり、かつての一兵士の物語はどこかで今のあなたにも繋がっているように思える。
むしろ、そうした繋がりを心に起こすことこそが「火を灯す」ということであり、また太陽がさそり座へと移っていく今週のしし座のテーマと言えるだろう。
圧倒的な闇の実感
岡崎京子の『Blue Blue Blue』には、
「匂いはいつもあやうい。ことばではない何か。何かが反応してしまう。匂い。夏の。夜の。アスファルトの。あなたの。匂い。」
という独白が出てくる。もし、これが馬鹿らしいほど明るい蛍光灯の下で吐かれたセリフだったなら、きっと読者もシラケてしまっていたはずだ。
まとっている闇が深ければ深いほど、その中で立ちのぼってくる感覚や印象は鮮烈になっていく。そういうことを、高度経済成長期前の日本人は当たり前に体感していたし、上手に楽しんでいた。
例えば、集まって月の出を待つ「月待」や、怪談を語りあう「百物語」、野山に繰り出す蛍狩りや虫聴きなど、実にさまざまな機会を持っていた訳だが、現代人はそのほとんど既に喪ってしまった。
掲句の「小さな灯り」という感覚もまた、みずからを包む圧倒的な闇の実感を感じ直すための契機であり、むしろそれを際立たせるための灯りなのだとも言える。
ただ、たとえ心許ない灯りであったとしても、やはり灯さないよりは灯した方がいいのだろうと思う。そうして初めて、人はどうにもならない現実を自分の胸にしまっていくことができるのだから。
今週のキーワード
言葉ではない何かが反応していくこと