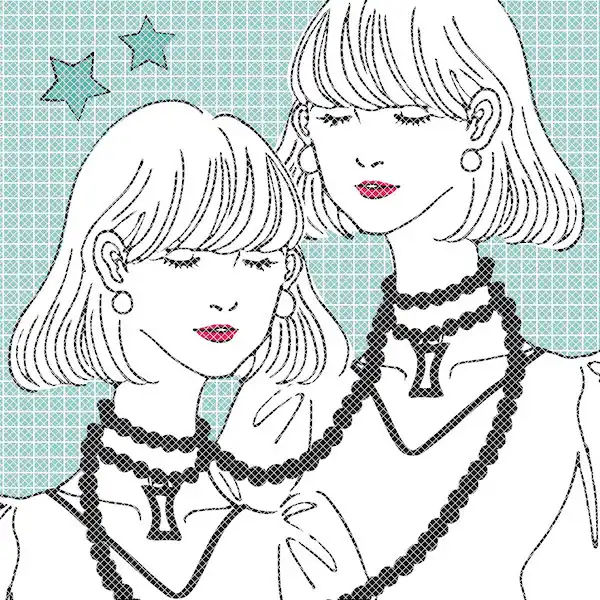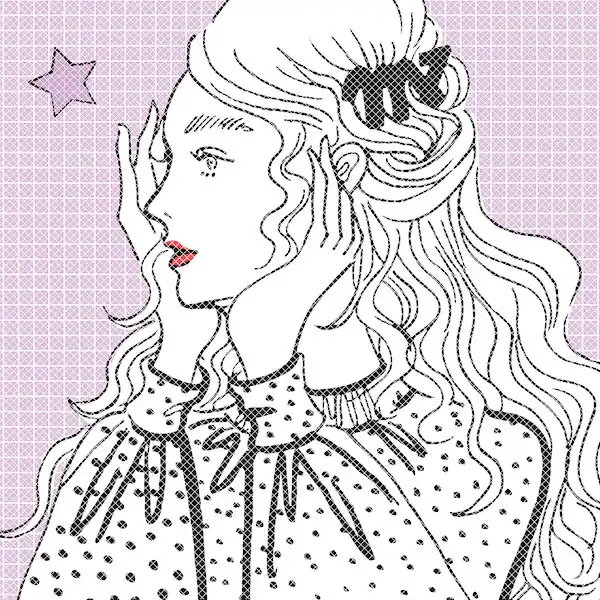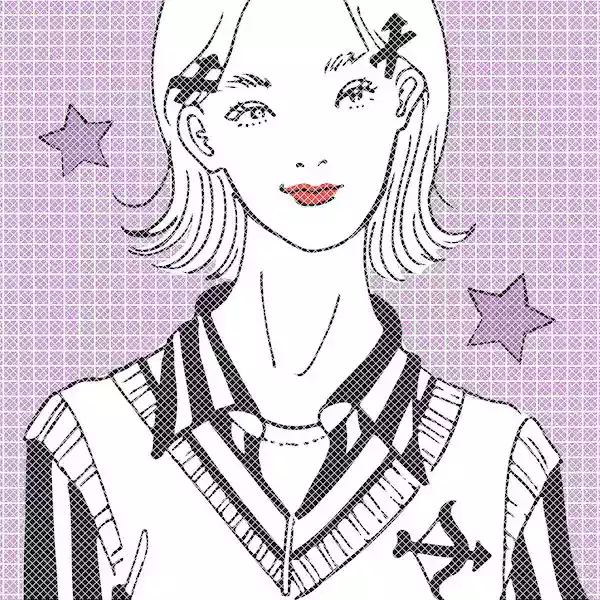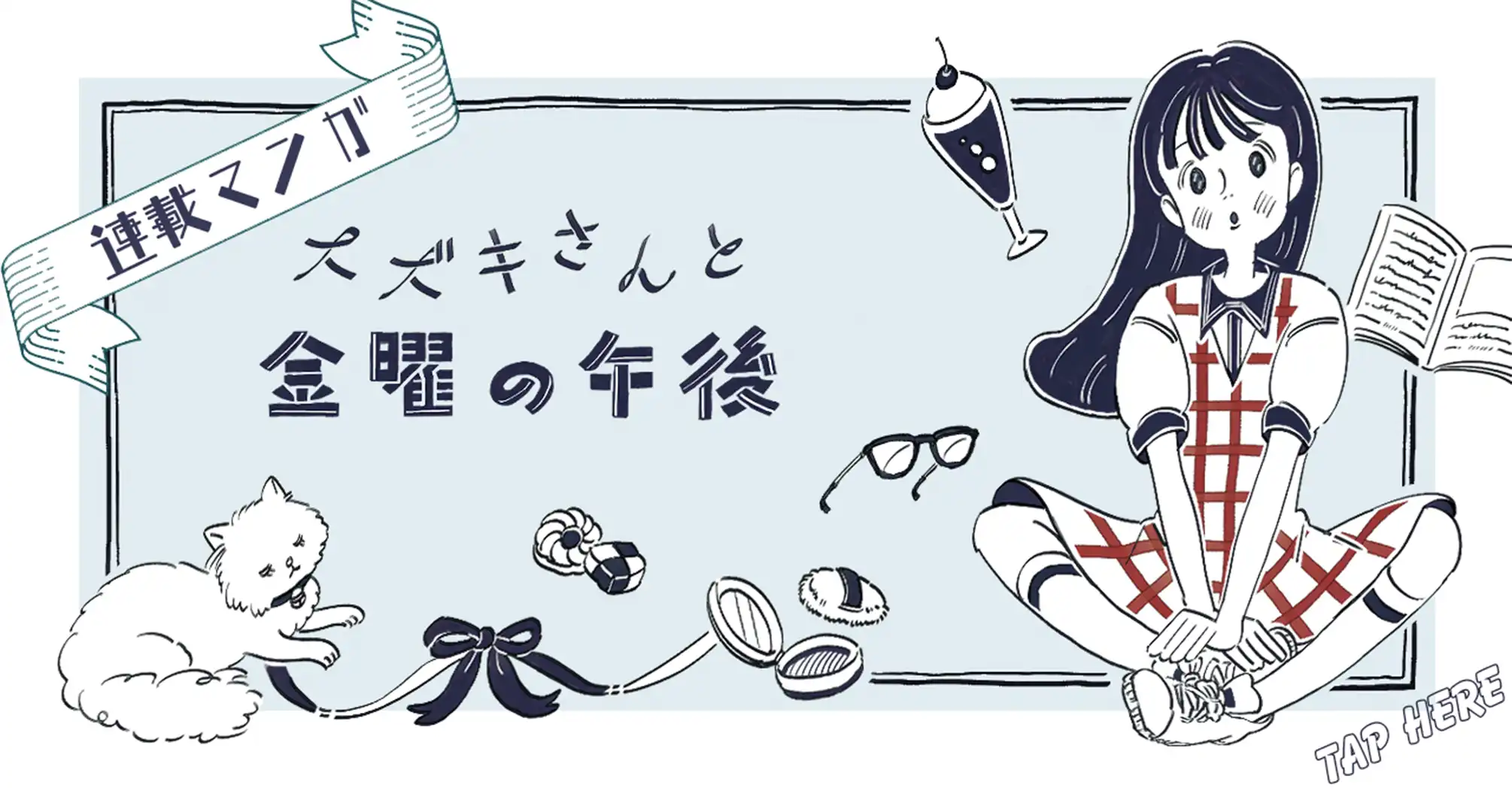みずがめ座
壊しえないものを見出す

蝶をつかまえる
今週のみずがめ座は、『青いとんぼ』の歌詞のごとし。あるいは、「フラジリティ」の核心に触れていこうとするような星回り。
かつて北原白秋はこの歌の歌詞に「青いとんぼの綺麗さは/手に触るすら恐ろしく」と綴りました。実際に蝶をつかまえてみると分かることですが、そこには言葉にするのが難しい独特の質感があります。
蝶の羽がはたはたと羽ばたける程度の空間を手で囲ってから、鱗粉をこぼさないようそっとすぼめつつ、小さくも柔らかい自由を蝶に与えてやる。蝶がはばたくと、くすぐったくて耐えがたいような思いに駆られるが、かといって手を固く閉じてしまうこともできない。
この、蝶と手のあいだのわずかな空間で起きている接触、そのおぼつかない感覚こそが、「フラジリティ」と呼ばれるものなのでしょう。すなわち、脆くて壊れやすいにも関わらず、決して消えてなくなることのない内的充実がそこにあり、透明で微細な抵抗力が宿っているのだとわかること。
同様に、6月29日にみずがめ座から数えて「自分なりの美学」を意味する6番目のかに座で新月を迎えていく今週のあなたもまた、自分がどれだけ外部から毀損されたとしても、これだけは失われないし、失うことはないのだと思えるものとは何かということを、一つ考えてみるといいでしょう。
アリアドネの糸
ミシェル・ビュトールの『時間割』という奇妙な小説があります。主人公ルヴェルは1年間の長期出張でイギリスのブレストンという都市にやってきたのですが、そこで次第に「脂じみた埃の巨大な沼」と描写されるこの迷宮のような街に飲み込まれ、自分を見失いかけてしまうのです。
すでにこの都市のかずかずの詭計(きけい)がぼくの勇気をすり減らし、窒息させていた、すでにこの都市の病いがぼくを包みこんでいたのだ。(中略)すでにあの日からぼくは理解したのだ、ブレストンとは、城壁や街道の帯ではっきりと区切られ、田野を背景にくっきりと浮かび上がった都市ではなく、霧のなかのランプにも似た、いわば暈(かさ)の中心なのであり、暈の拡(ひろ)がりゆく外縁はほかの都市の外縁と結びついているのだということを。
しかし、そんな雨降りの街の中心で、「ぼく」は日記を書き続け、それがやがて本書となって読者はそれを後追い読んでいるのだということに気が付きます。
多くの文章が一本の綱となってこの堆積のなかにとぐろを巻き、5月1日のあの瞬間へとぼくをまっすぐに結びつけている、5月1日のあの瞬間、ぼくはこの綱を綯(な)いはじめたのだ、この文章の綱はアリアドネの糸にあたる、なぜならぼくはいま迷宮のなかにいるのだから、迷宮のなかで道を見いだすためにぼくは書いているのだから。
ここではいわば、都市が手となり、フラジリティの中心には「書くこと」があるのだと言えるのではないでしょうか。同様に、今週のみずがめ座もまた、小説内の「ぼく」のように「語り」を通して自分なりの壊しえないものを見出していくべし。
みずがめ座の今週のキーワード
都市と「ぼく」のあいだのわずかな空間で起きている接触