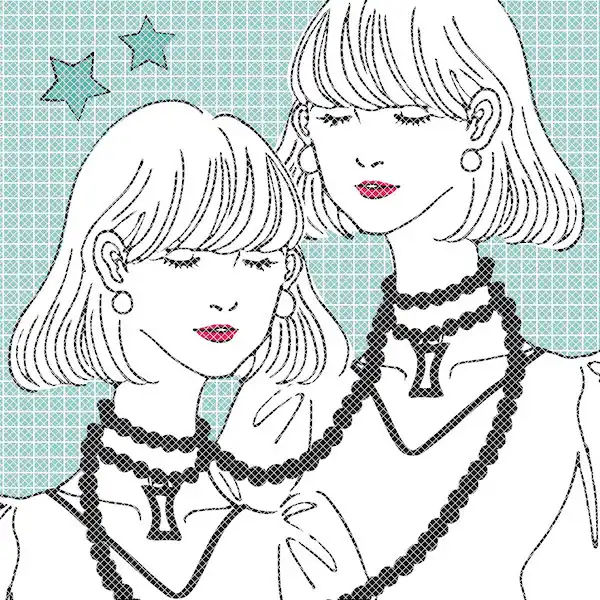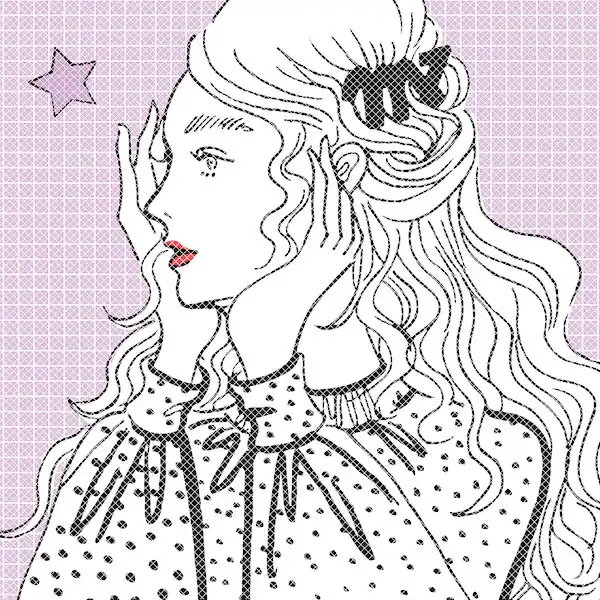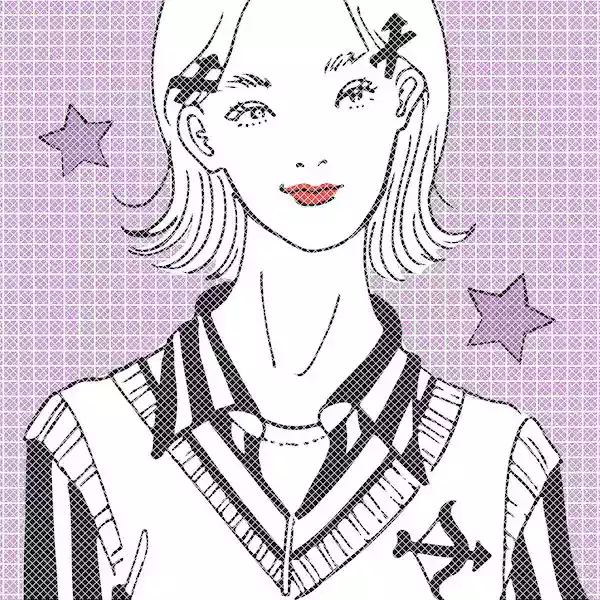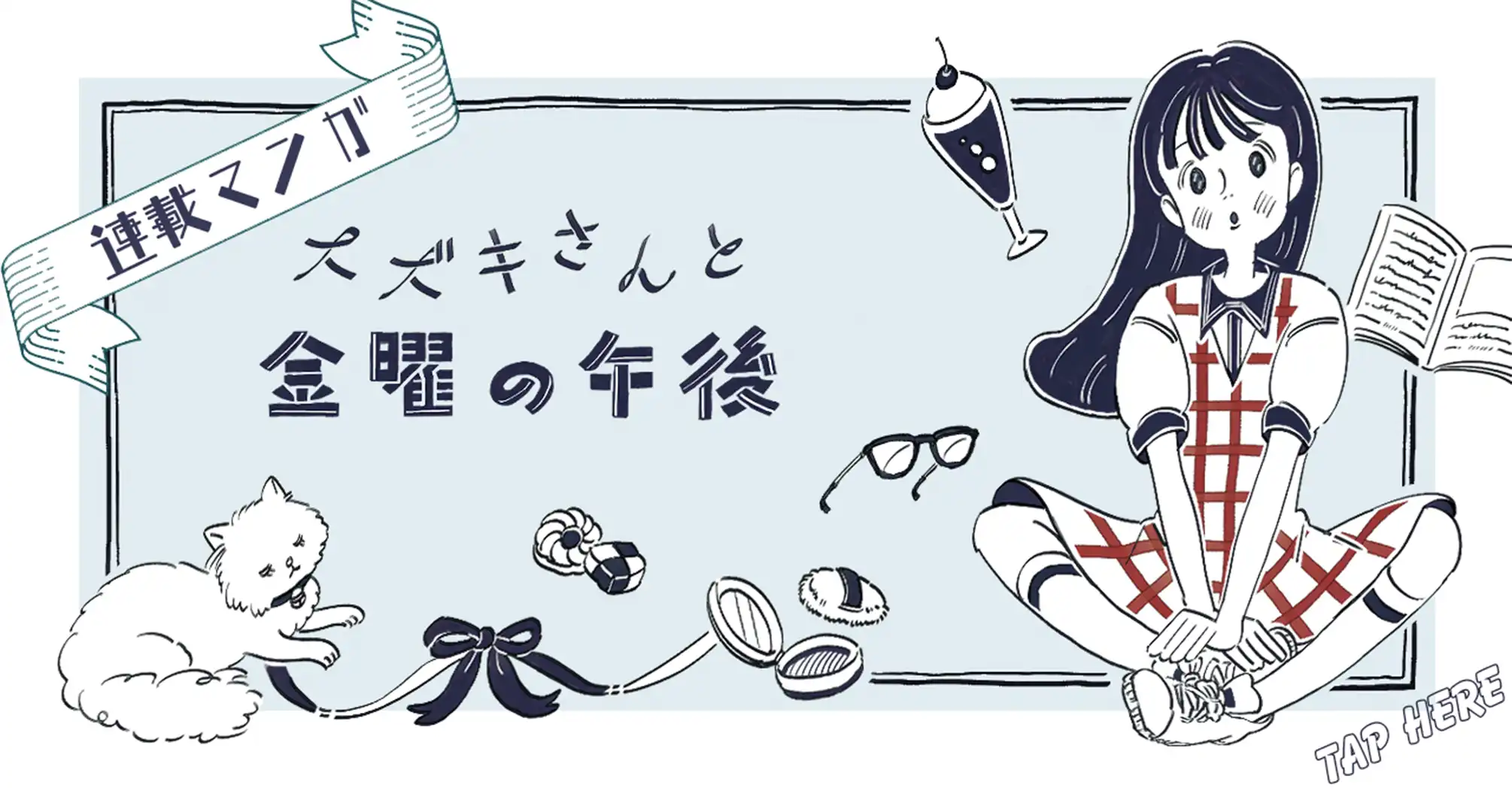さそり座
悲哀をぶつける

残された心
今週のさそり座は、『死なば世に忘らるる身か月の秋』(小山良一)という句のごとし。あるいは、死にゆく流れと生まれくる流れが同時に流れていくような星回り。
戦地で病死した或る一兵卒の作。生きていれば、親を見送り、妻をめとり、子を得て、自分の家をなしたかもしれない、けれどそうしたことをすべて為さず、わずかな遺句のほかは何一つ残さず逝ってしまったのだという。
「死なば世にやがて忘らるる身なのだろうか」という自問自答には、忘れられても忘れられなくても同じではないか、悠久の宇宙生命から見れば人の命などうたかたに過ぎないではないか、という投げかけがセットになっていますが、実際のところ、異国の土地で病に倒れ、月夜の晩に自分が生まれた世界からまったく無関係になってしまうことを想像している作者の姿を想像してみると、その背中のさびしさは尋常ではありません。
むろん世に忘らるる者も、忘られぬ者も、死ぬときがくれば皆等しく死んでゆく他なく、もう死んでしまった者にとっては、忘れられているか否かは何の関係もない訳です。あるとするならば、私たちの方にでしょう。すなわち、生き残っている側にとっては、かつてこの世に生きたこれという人の残された心が、忘れられないでいるだけなのです。
古代ギリシャの格言に「芸術は長し人生は短し」というものがありますが、その長い芸術を残した者さえも、「死なば世に忘らるる身」の悲哀をどうすることもできず、悠久の時の流れの末にやがては無名へと帰していくのでしょう。
12日に自分自身の星座であるさそり座に火星が入っていく今週のあなたの中にも、そんな忘らるる者と忘られぬ者との2つの哀歌がとうとうと心中を流れていくはず。
ひとりでは泣くに泣けない
ギュンター・グラスの長編小説『ブリキの太鼓』では、戦中から敗戦後にかけてのドイツ社会解体の混乱が、緻密かつぶざまに、ときにグロテスクなユーモアをまじえて描写されているのですが、その中にライン河畔の市にある「玉ねぎ地下酒場」の場面があります。
酒場ならばビールやワインが飲めるばかりでなく、ちょっとした料理が食べられるのが普通ですが、ここではそういうものは一切出ません。客のまえには、まな板と包丁が並べられ、そこに生の玉ねぎが配られるのみ。つまり、このまな板の上で各自めいめいが玉ねぎの皮をむき、好きなように切り刻んで、それをご馳走にしろという、なんとも人を食ったシステムなのです。
ただ、こうしたバカバカしいことをするために、わざわざ料金を払ってやってくる客がいるのも事実。それは一体どういうことかと言うと、玉ねぎを切れば客の目には涙が流れる訳ですが、それがミソになっていると。
その汁がなにを果たしてくれたのか?それは、この世界と世界の悲しみが果たさなかったことを果たした。すなわち、人間のつぶらな涙を誘い出したのだ。
今週のさそり座もまた、自分ひとりだけではどうにもできない悲哀を、誰かや何かの力を借りて然るべき仕方でぶつけてみるといいでしょう。
さそり座の今週のキーワード
何の役にも立たない、バカバカしいことをあえてする