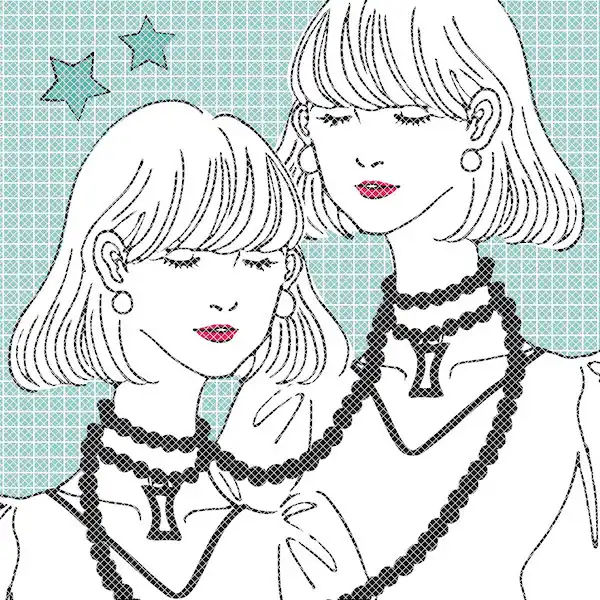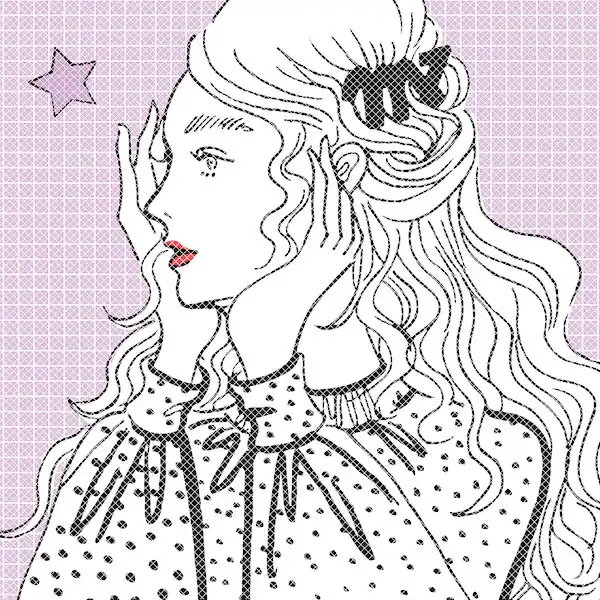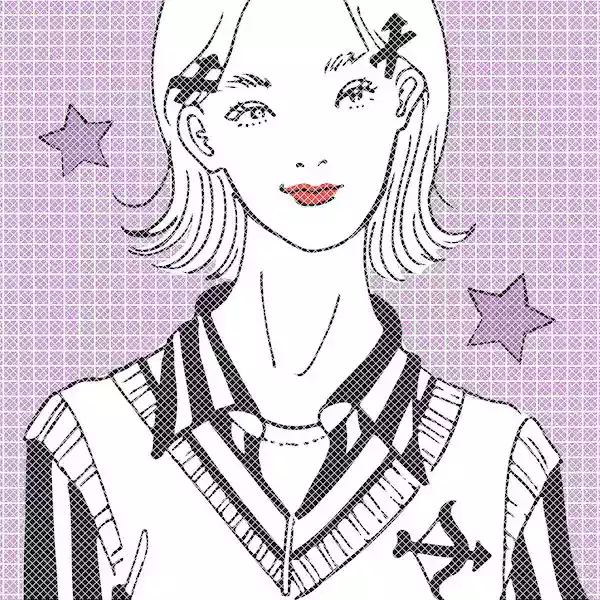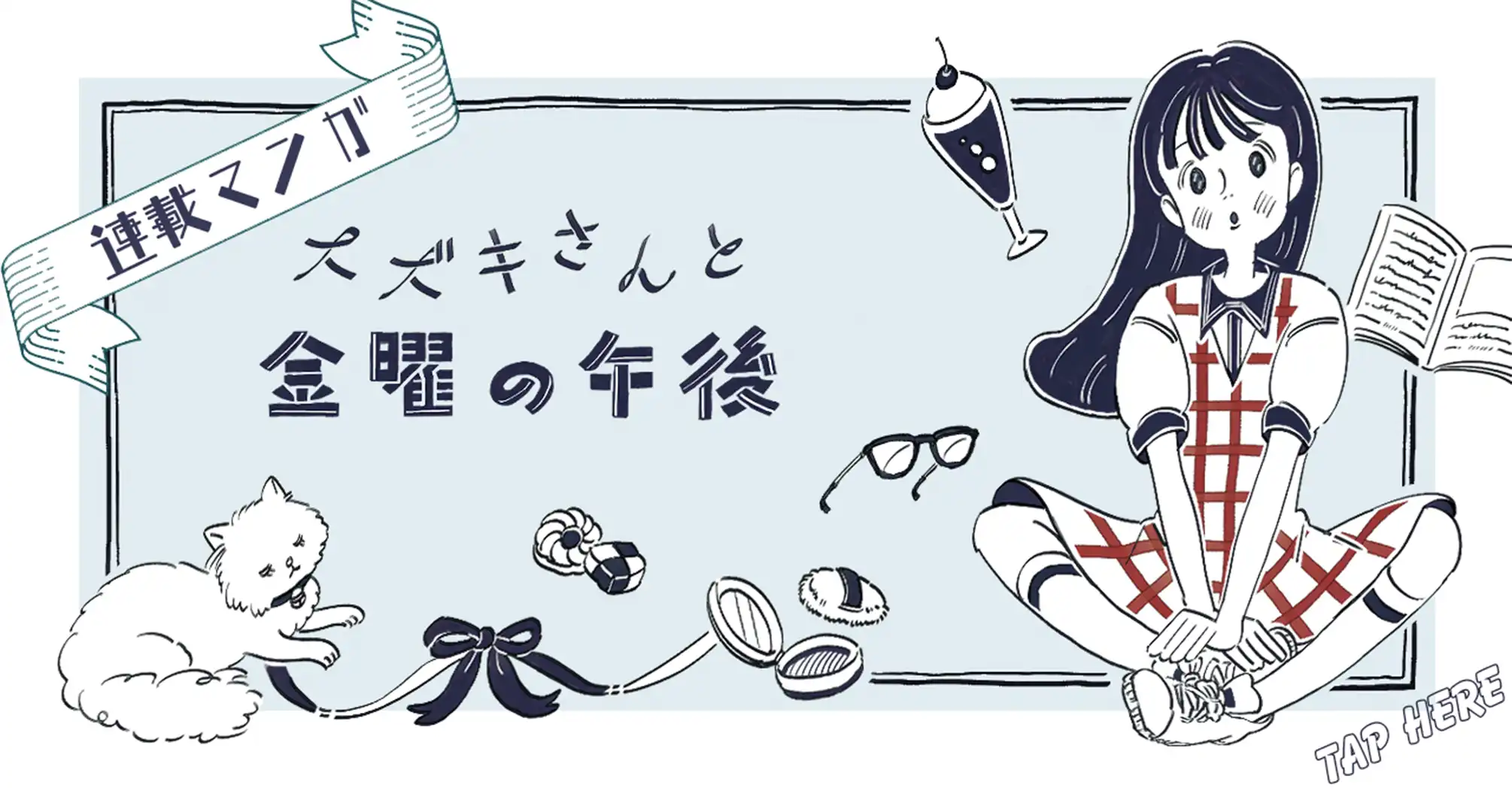しし座
喰らい、喰らわれ、絡み合う

食事風景の輝き
今週のしし座は、パリの馴染みの店でビールを飲むヘミングウェイのごとし。あるいは、ただただ飲み食いを堪能し、英気を養っていこうとするような星回り。
第一次大戦後のパリには、まだ無名の若いアメリカ人の作家希望者たちが集まり、日々の暮らしを楽しみながら、来たるべきアメリカ文学の黄金時代の土台固めをしていました。中でも、ひときわ輝かしい存在であったのが、アーネスト・ヘミングウェイでした。
彼が不幸な自殺を遂げた後、遺作として発表された『移動祝祭日』には、このパリ時代の思い出を回想しつつ、当時の溜まり場での生き生きとした描写を次のように綴っています。
そのビールの飲める店には、あまり客がいなかった。鏡のついた壁を背に、テーブルを前にして、ベンチに座るとウェイターが、ビールですかと聞いた。私は、ディスタンゲ―一リットル入りの大きな取っ手付きグラスと、ポテト・サラダを注文した。ピールはたいへん冷たく、おいしく飲めた。(…)最初に大きくグッとビールをひと飲みしてから、私は極めてゆっくり飲んだり食べたりした。油いための馬鈴薯がなくなってしまうと、もうひと皿と、セルブラを注文した。これは一種のソーセージで、どっしりとした幅広いフランクフルトを二つに裂いて、特別なカラシのソースをかけたようなものだ。私は油やソースを全部、パンでふきとり、ビールをゆっくり飲んでいるうちに、とうとう、ビールがぬるくなり始めたので、私はそれを飲み干し、今度はドミ(半リットルのコップ)を注文し、それにビールが注ぎ込まれるのを見つめていた。それはディスタンゲより冷たそうに思われ、私はその半分を飲んだ。(福田陸太郎訳)
15日にしし座から数えて「生きがい」を意味する2番目のおとめ座で新月を迎えていく今週のあなたもまた、存分に味覚的体験世界を深めていくべし。
中世における「味覚」の位置づけ
人生いかに生くべきかという問題について深く考えたければ、『聖書』や『論語』を読むべきだと言う人は多いでしょうけれど、しかし『聖書』や『論語』にしても、飲み食いのことは決しておろそかにしていないどころか、これらの聖典の作者たちのなかには、味覚のかなり発達した人びとがいたのではないかと思わせる文章は枚挙に暇がありません。
例えば、キリスト教神学の大成者で天使博士とも呼ばれたトマス・アクィナスや彼と並び称されたボナヴェントゥラなど、中世の二大神学者はいずれも「味覚」を肉体的感覚の中で、つまり視覚、聴覚、嗅覚、触覚らにおいて最も基礎に位置づけており、味覚が豊かでなければ他の感覚の力は弱いものになると考えていました。
そして、味覚の中でも特に重要視されたのが、甘いことと苦いこと、並びにそれらを識別する能力でした。精神を陶酔にいざなう「甘美さ」は人間が感じるあらゆる喜悦の中で最も基本的なものであり、それは「甘さ」を通じて得られるものだったのです。また、「苦さ」とは人間が神を見出すための渇きや苦労の味わいであり、痛恨や悲哀もまた「苦さ」のなかに含まれているものとされたのです。
今週のしし座もまた、ただただ腹を膨らますだけでなく、そうした霊的なものへの味覚ということも、念頭に置きつつ過ごしていくといいでしょう。
しし座の今週のキーワード
甘さと苦さは2つでひとつ