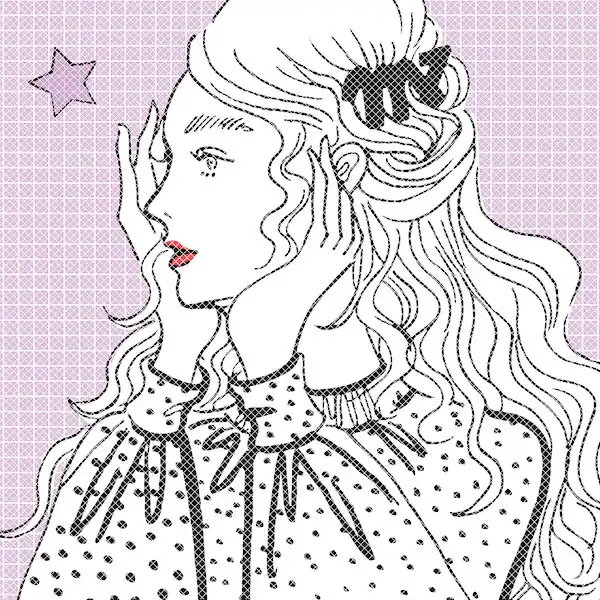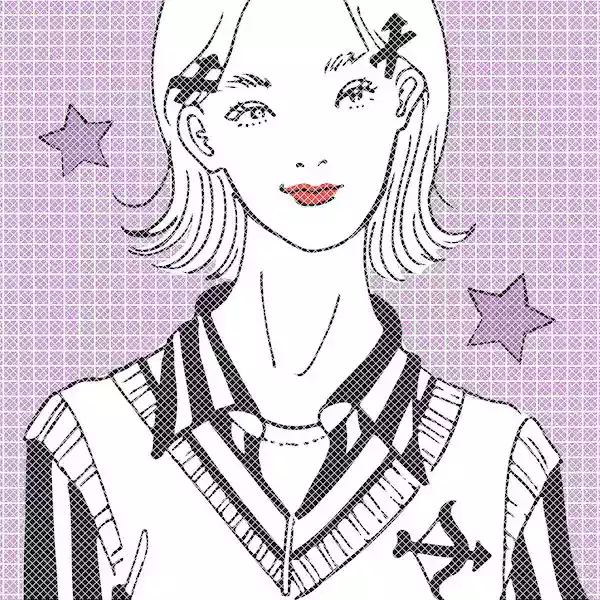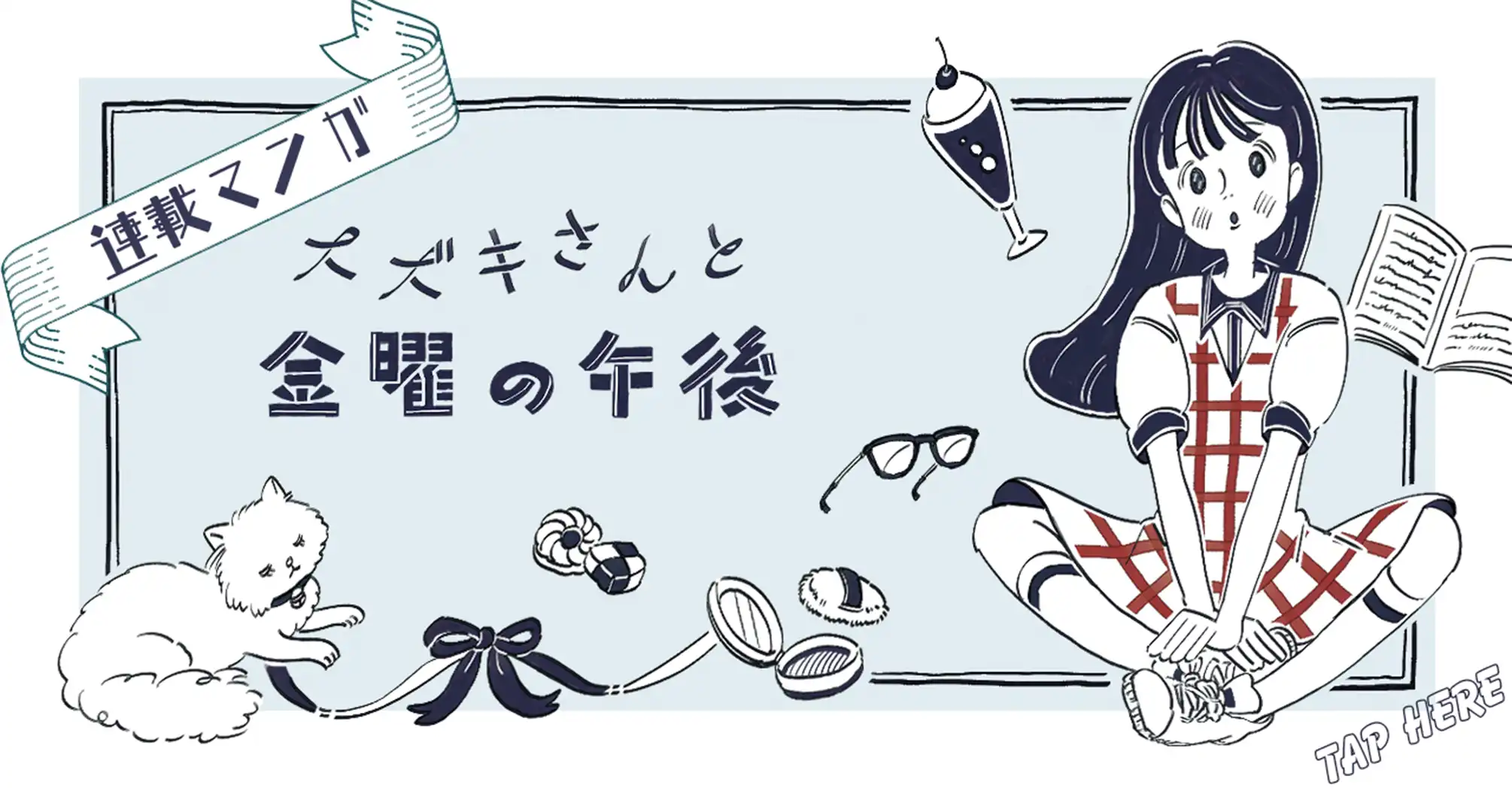ふたご座
歩行から舞踏へ
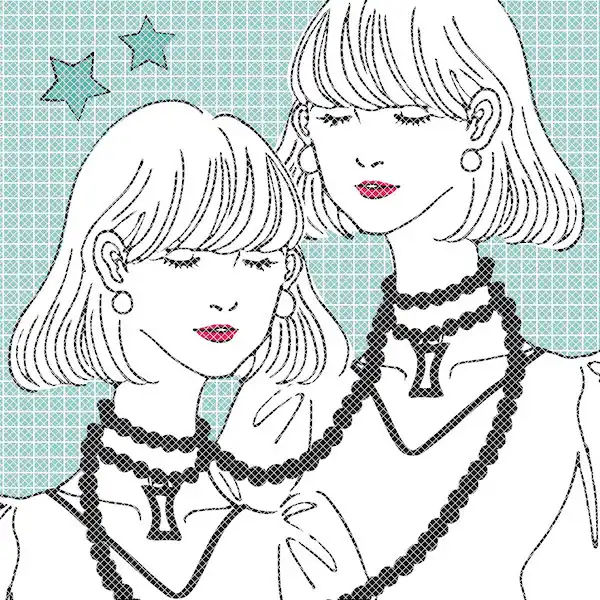
喪失と回復への誘惑
今週のふたご座は、「散文から詩への、言葉から歌への、そして歩行から舞踏への移行」のごとし。あるいは、天使も踏むのを恐れる一歩を踏み出していくような星回り。
これは20世紀ヨーロッパの最重要詩人の一人であるポール・ヴァレリーの断章集「一詩人の手帖」(松田浩則訳)からの引用ですが、詩は何もロマンティックな修飾語の多用によって詩となるのではなく、ただもろもろの観念のうち散文の中には置いておけない部分が詩と呼ばれるのです。
つまり、「思考のあまりに活発で、あるいは律動的で、あるいは無反省な動きのなかでしか可能ではない観念」が自然と散文とは異なる形態を伴っていくというわけ。
ヴァレリーは冒頭の言葉に続けて、「この瞬間は行為であると同時に夢なのだ。舞踏は、わたしをここからあそこまで移動させることを目的とはしていない。純粋な詩句や歌も同様である」と述べていますが、それは行為が「わたし」という主体の占める場所に取って代わり、行為の最中で「わたし」を見失い、それまでとは別の場所に再び「わたし」を見つけるという、喪失と回復とが詩にはつきものなのだということではないでしょうか。
逆に言えば、最初に計画を立ててそのあとをついていくのであれば、それは詩ではなく説明文であり、例えば青い鳥を探しに行くというおとぎ話もまたそこでは成立しないのです。
20日に太陽がふたご座から数えて「入れ替わり」を意味する11番目のおひつじ座に移動し、春分を迎えていく今週のあなたもまた、平板な言葉の記述ではなく思い切った主体の飛躍を試みていくことになるでしょう。
優位感覚の交替
一般的に、失明すれば文字も読めなくなり、創作活動も難しくなると考えられがちですが、実際に著名な詩人などを見ていくと、むしろ逆の例が多くあることに気づかされます。
例えば、イングランドの大詩人ミルトンは、44歳で過労のために失明した後、50歳で代表作となった一大叙事詩『失楽園』の制作に着手して9年後に刊行しましたが、その他の詩人としての業績もほとんどすべてが失明後に書かれたものでした。
もちろん、ホメロスのような描写がきわめて視覚的な詩人というのも多い一方で(ただ彼はその伝説において盲人だった)、聴覚的で音楽的であることは詩の本分であり、ボルヘスによれば視覚的でない詩人こそが「真に知的な詩人」なのだと言います。
ミルトンの失明は自発的なものでした。彼には自分が大詩人になる予感があり、失明したことでそれが確信に変わったのです。ミルトンがソネットにおいて自分の盲目について語っている箇所では、「in this dark world and wide(この暗く広い世界に)」とありますが、今週のふたご座もまたそうした“一線の踏み越え”がテーマとなっていきそうです。
今週のキーワード
今まで生きてきた中で一番丁寧に歩いてみる