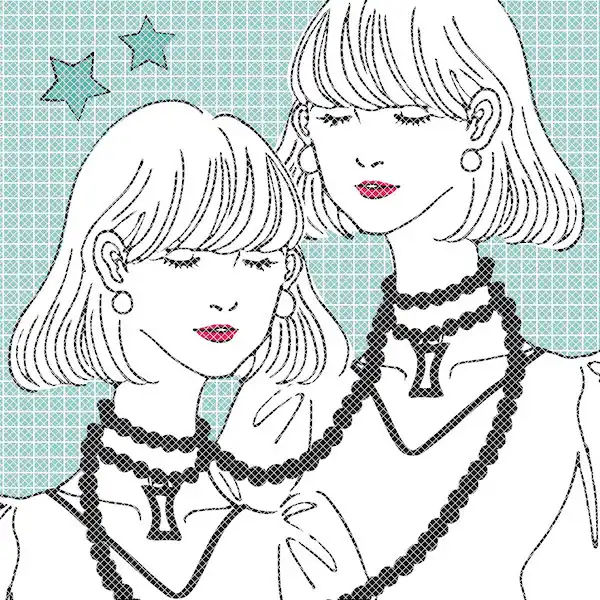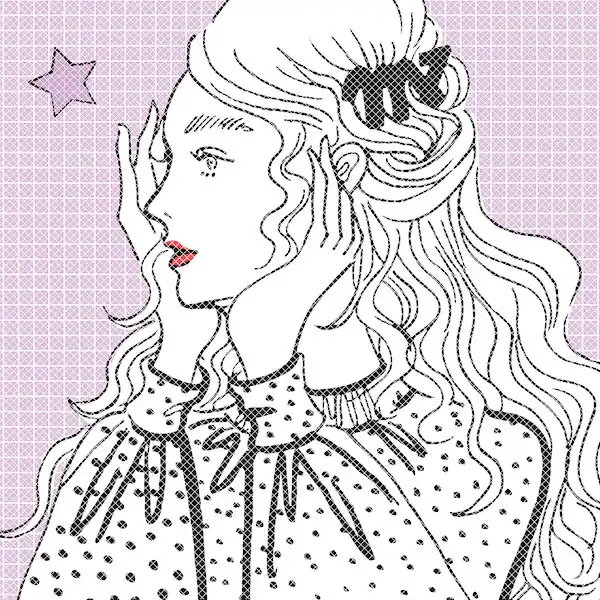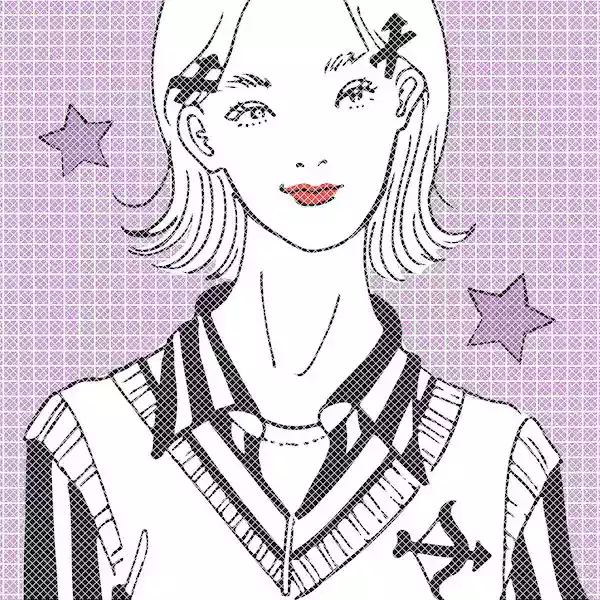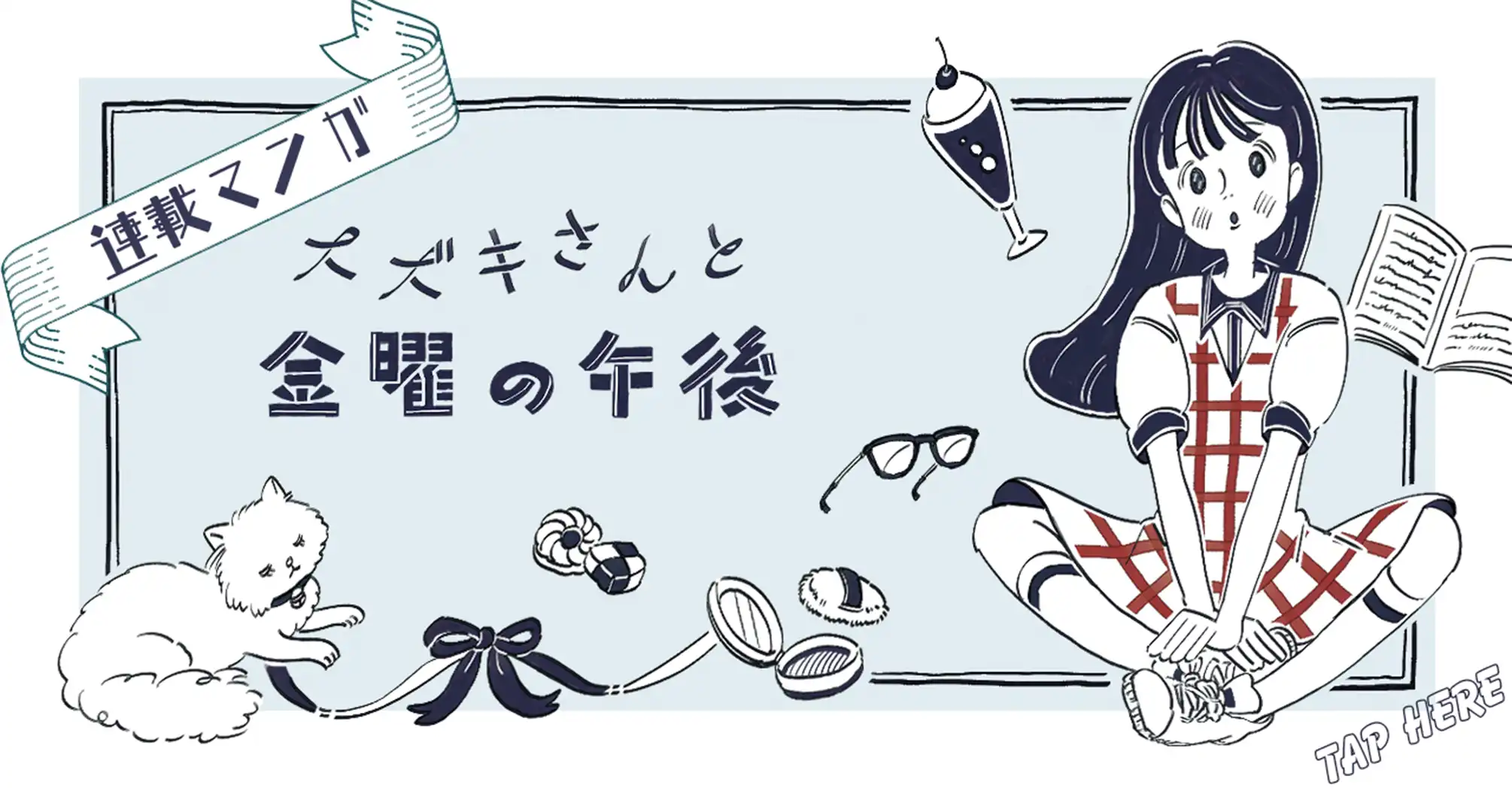やぎ座
予定調和の“外”へ

意外な発見に開かれる
今週のやぎ座は、『突兀として少年らストーヴに』(小川芳江)という句のごとし。あるいは、想定外の現実に目の覚めるような思いで直面していくような星回り。
「突兀(とっこつ)」は、岩などがごつごつと突きでている様をあらわす語。だとすると、この形容詞から「少年ら」という展開には飛躍があり、意外性にもとづく発見がある。
つまり、数人でストーヴを囲んでいたのが少年らではなく、青年らや男衆というのであれば意外性はうすらぐし、おそらくは句にもならなかったはず。
じっとして集団で暖をとっている時には、ふるさびた岩がごろごろ転がっているように見えたというのだから、冬着でかさを増した図体は十分りっぱなものだったのだろう。だが、彼らのつややかな肌や赤くそまった頬はあきらかに幼く、それがある種の異様さをもって作者を圧倒し、飲み込んでしまったのかも知れない。
現実というのは、しばしばこうした仕方で何でもないような顔をして、不意にわたしたちの想像を裏切り、手玉にとってくる。考えてみれば、「ういういしい少年」などという言葉で普通私たちが思い浮かべるようなところには、彼らはいないのだ。
2月3日にやぎ座から数えて「交流」を意味する11番目のさそり座で下弦の月を迎えていく今週のあなたもまた、そうした見慣れた検索ワード化した頭の中の言葉たちの“外”へと突き抜けていくべし。
ヴェルナー・ヘルツォークの『氷上旅日記―ミュンヘン‐パリを歩いて―』
中世の巡礼者たちは、聖地に向かって数百キロから時に1000キロ近い距離を徒歩で歩いたと言います。そしてドイツの映画監督であるヘルツォークが、映画人としての自分を育ててくれた恩人の女性の重病を告げる電話をとった瞬間に決めた、磁石だけを頼りに決行したミュンヘンからパリへの徒歩の旅も、自分の手には負えない災厄や悲しみを和らげるための行為という意味では似たようなものだったのではないでしょうか。
氷や雨や雪や暴風のなかを、濡れそぼち、骨まで氷りそうになって、憑かれたように彼は歩く。まるで、歩くことによってだけしか、大切な友人は生き延びられないと信じているかのように。そして旅人が夜を過ごすのは大抵は無人の別荘や、農家の干し草小屋でした。
窓から外を見ると、むかい側の屋根の上にカラスがとまっていた。雨のなか、首をちぢめ、身動きもしないで。しばらくたってからも、あいかわらずじっとしたまま動かず、寒さで凍えながら、静かにカラス的思索にふけっていた。眺めているうちに、不意に兄弟のような感情が湧いてきて、一種の孤独感で胸がいっぱになった
歩き始めてから21日目。パリにたどり着いて訪ねた恩人は生きていた。
ほんの一瞬のあいだ、死ぬほど疲れきったぼくのからだのなかを、あるやさしいものが、通り過ぎていった
今週のやぎ座もまた、普段なら何も感じずに通りすぎてしまうところを、あえて迂回したり、巡礼していくことを選んでいきたいところです。というのも、そういう真に不合理かつ人間的な選択を通してしか、自分自身の救済というのは促されていかないから。
やぎ座の今週のキーワード
監督から主役への転回