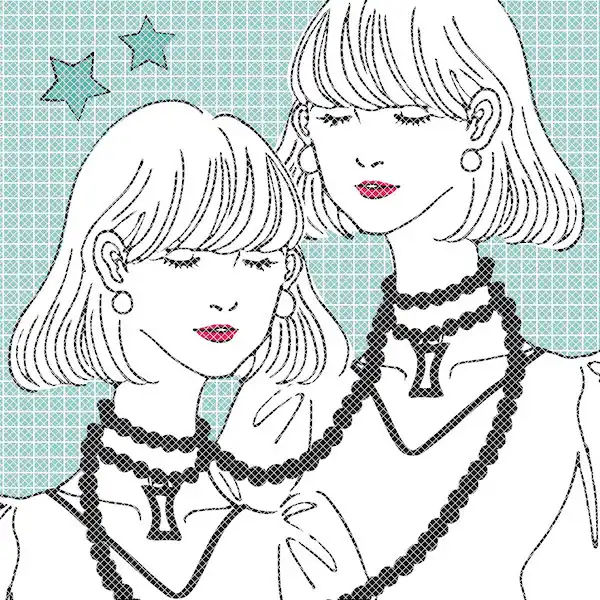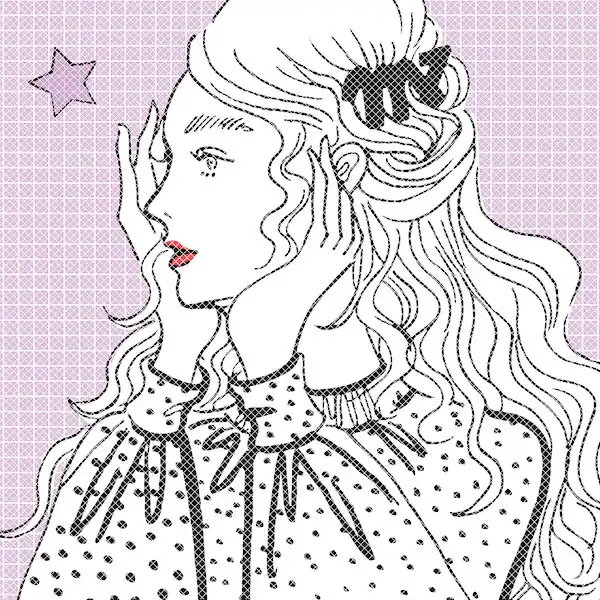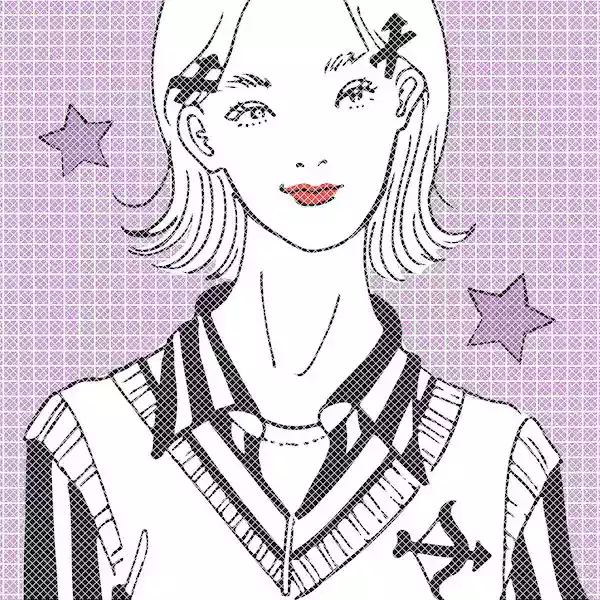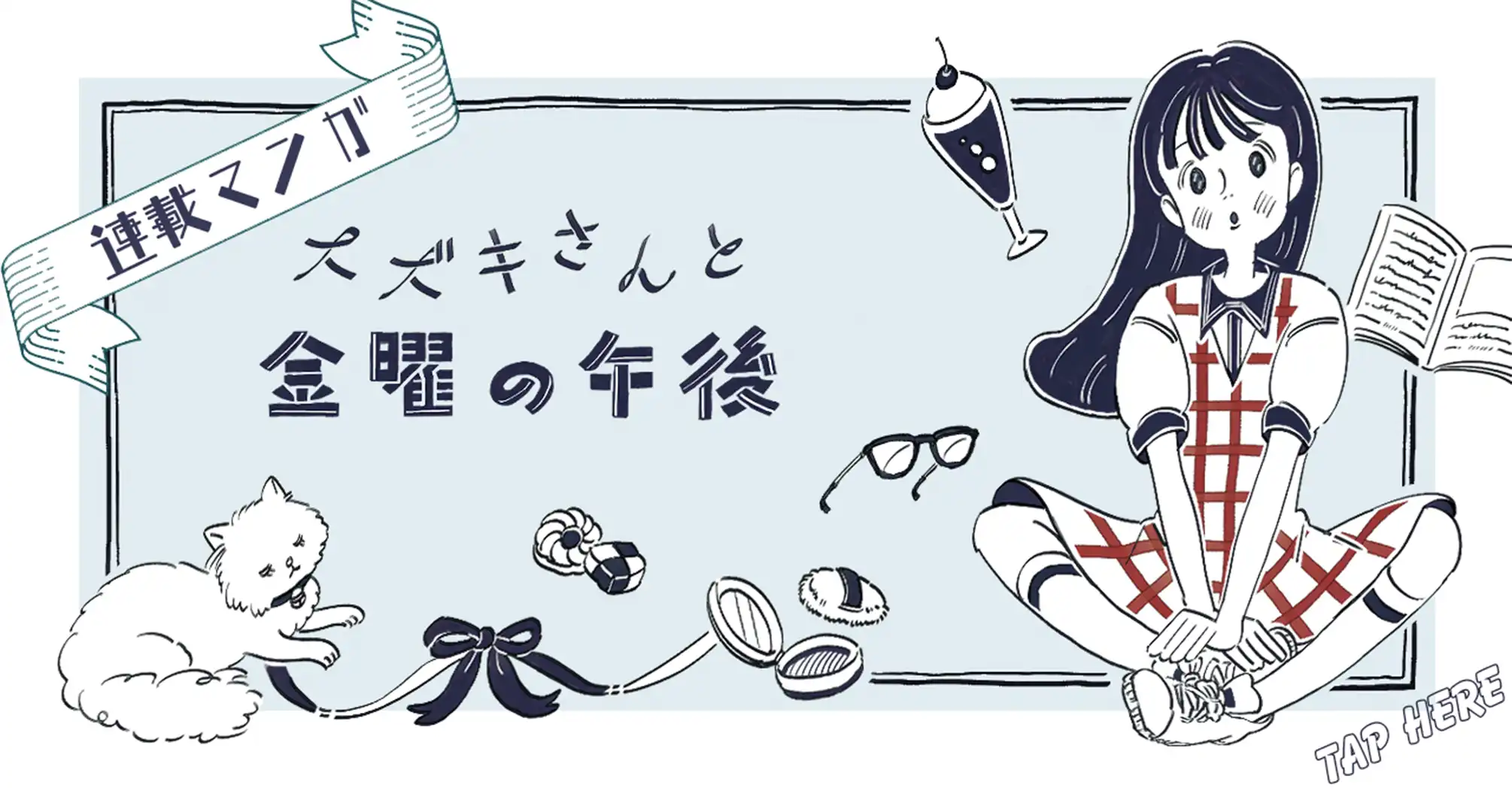かに座
ラディカルな抵抗を

肉を斬らせて骨を断つ
今週のかに座は、「裏の闇である私」となって語るアーレントのごとし。あるいは、強いられた共同性から脱け出すための方途を探っていこうとするような星回り。
1963年に『ニューヨーカー』誌に連載され、その後アメリカの出版社から刊行されたハンナ・アーレントの『イェルサレムのアイヒマン―悪の陳腐さについての報告―』は、元ナチの戦犯で、ユダヤ人撲滅作戦において数百万人におよぶ強制収容所への移送を指揮したアイヒマンの裁判をみずから傍聴し、膨大な関連資料を読み込んだ上で書き上げた大作ルポでした。
しかし、本書は発表直後から欧米のユダヤ人社会を中心に大きな議論を呼び、その後一連の激しい著者個人への非難キャンペーンの端緒となったいわくつきの仕事であり、その際「しばしばほとんど嘲弄的で悪意ある」と非難されたのが自身もユダヤ人であるはずの彼女の語り口でした。
それは資料によりながら、淡々と叙述を重ねていく一方で、「アイヒマンの味方なのか」という評まで生んだほどに、ときにアイヒマンに非常に深くコミットし、可能な限りアイヒマンに沿って物事を理解しようと試みるかのような記述があったり、悲劇的状況に置かれた「同胞」への同情に欠ける『ニューヨーカー』誌にふさわしい硬質でしゃれた文体や、皮肉と風刺をまじえた乾いた語調からなっていたのです。
なぜ彼女は内容に工夫を凝らす代わりに、そうした語り口をあえて選び、訴えたのか。文芸批評家の加藤典洋は『敗戦後論』に収録された「語り口の問題」の中で、「わたしの考えをいえば、アーレントはこの裁判を、第三者として、それこそ冷静に、ルポルタージュしぬこう、そのことができれば、それはそれだけでなにごとかだ、と考えて」いたのだとした上で、次のよう述べてみせました。
共同性を殺すには共同性の単位である「私」の場所から、裏の闇である私となって語るしかない。私の語る言葉とは何か。私性は世界から奪われた存在にほかならない。私は言葉を奪われている。私に残されているのは語り口なのである。
ここで言う「共同性」とは、「この裁判を全世界の人間にもう一度ユダヤ人絶滅の悲劇の事実を知らしめ、頭を垂れさせる教訓劇に」しようとするユダヤ人社会の意向を宿した検事の語り口であり、彼女の語り口はそこから完全に欠落しているものをあえて引き受けたものだったのではないか、と。
7月28日にかに座から数えて「脱・共同体」を意味する11番目のおうし座で下弦の月を迎えていく今週のあなたもまた、自身の取るべき「語り口」ということをひとつ考えを巡らせてみるといいでしょう。
「生産性」という概念に対して
「生まれてきた以上は世の中に必要とされている人間だ」
「今、いのちがある限り、君には必ず使命がある」
これは現代社会では見慣れ切ったメッセージであり、「使命」などと大仰な言葉が使われているのも、要は「責務」という言葉の言い換えでしょう。
すなわち「生産性のない人間には生きる価値はない」というどこかの誰かの発言の裏返しでもあり、なんだかんだと言えど、今日の日本社会で広く受け入れられている生産性信仰に基づくじつにありふれた思想の表明と言えます。ああ、素晴らしきかな“不断の努力”とそれを疑うことなく価値づける労働倫理!
しかし、ほんらい生はどこまでも無根拠であり、無底。つまり、あらゆる意味付けや解釈を無効化し、価値という尺度を拒絶する地獄の底の奇蹟であり、どんな負債からも自由な“語りえない”何かであるはず。
今週のかに座もまた、自分が投げ込まれ硬直しつつある既存の文脈に抵抗し、そこから飛び出していくためのきっかけをつかんでいくことがテーマとなっていくでしょう。
かに座の今週のキーワード
水面の上をはねる魚