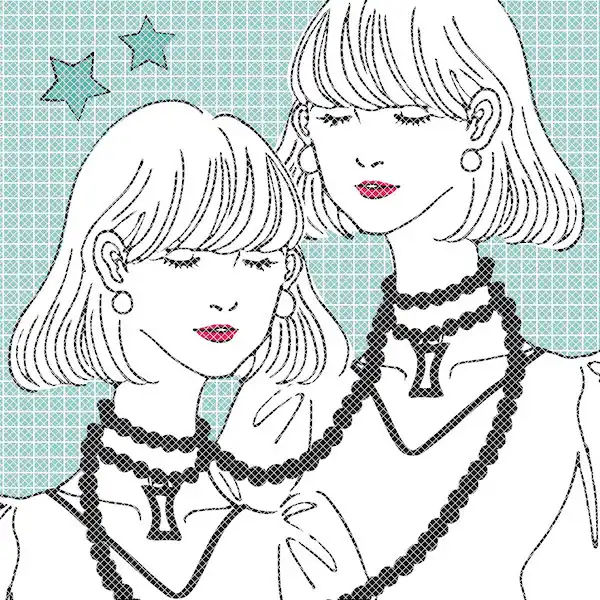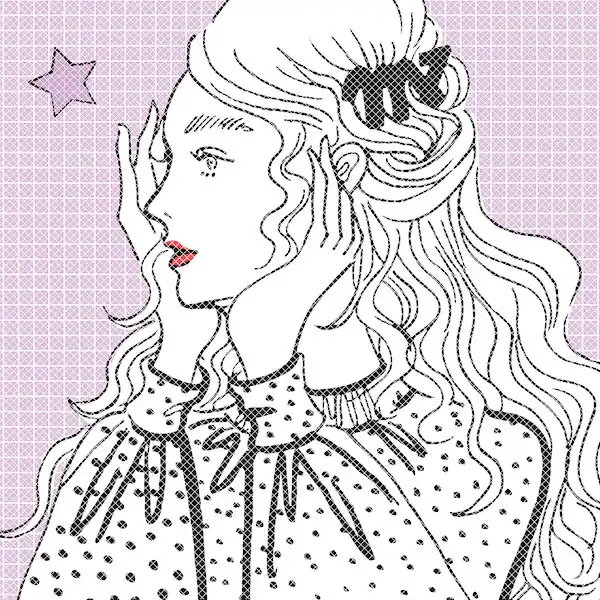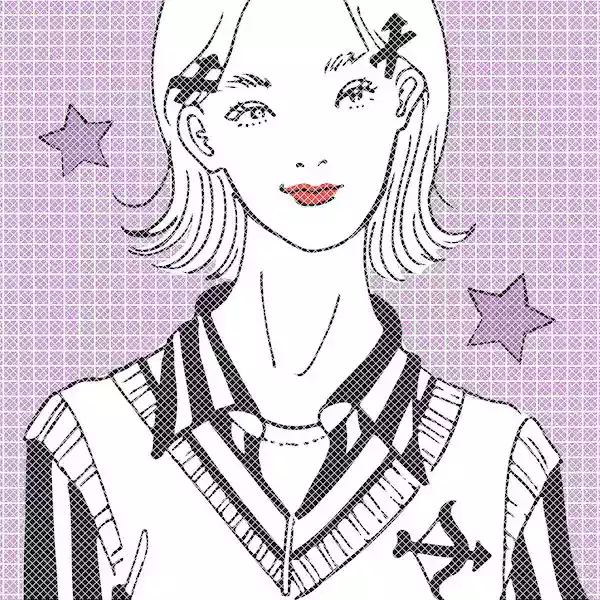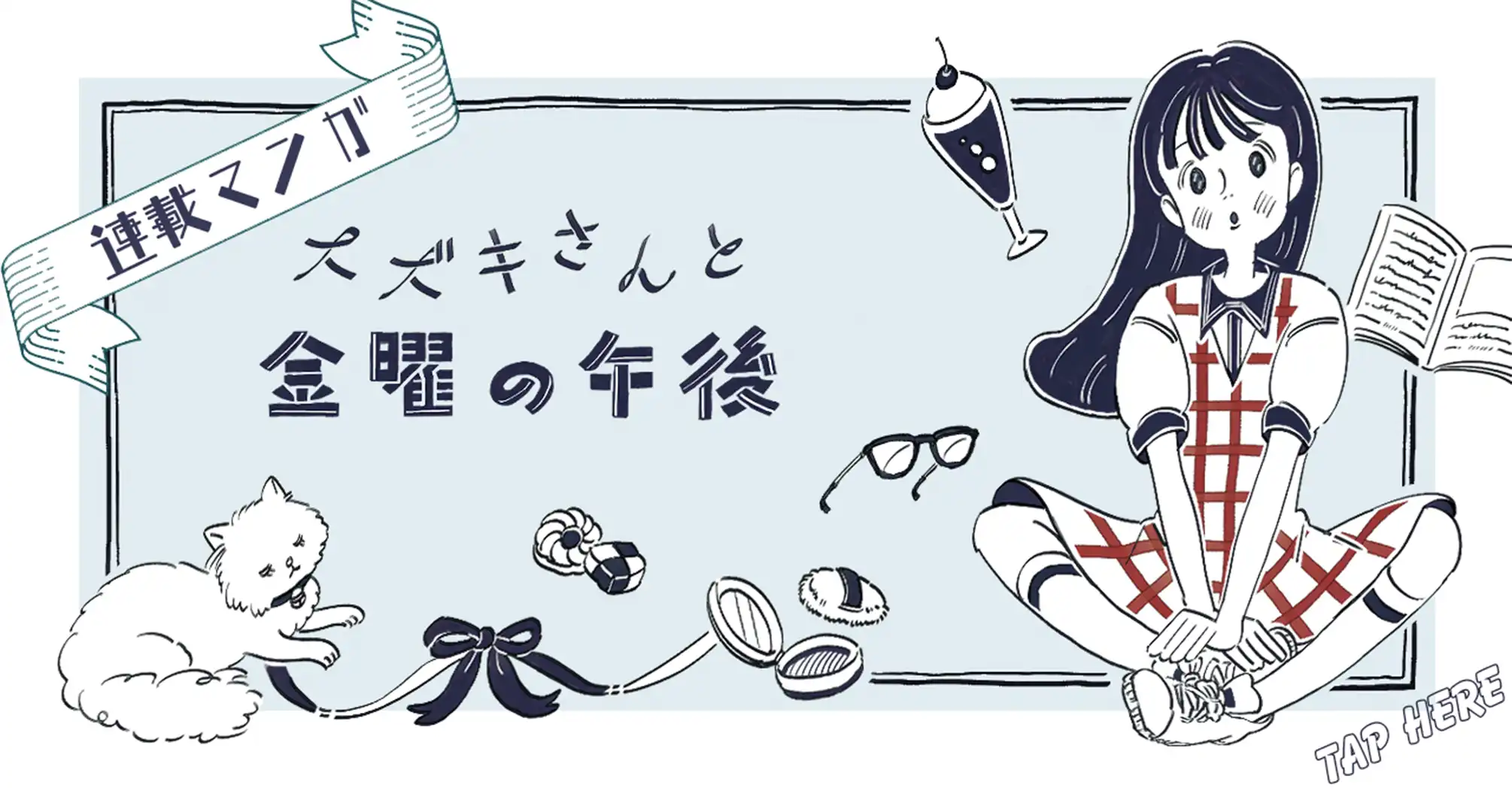おうし座
未知におのれを浸す

蟷螂賛歌
今週のおうし座は、「蟷螂のまなこ大きく枯れにけり」(本宮哲郎)という句のごとし。あるいは、自らの向き合うべき運命をその目に映していくような星回り。
現代の私たちは、蟷螂(かまきり)において、緑のカマキリと褐色のカマキリは2つの別々の種類であることを知っている人も多いですが、むかしの人は緑のカマキリが冬になってくると枯れて茶色くなるのだと考えて、それを大層おもしろがっていたのだと言います。
虫もまた草や木の葉のように枯れるものという前提で見たならば、掲句の「蟷螂」が枯れて大きくなったその目をくわと広げつつ、眼前に広がる枯れ野を見つめているその姿には、確かに簡単には見過ごせない何かがあります。
何かがみずからを決定的に変えてしまう時、人はそこに運命の介在を見出しますが、我が身を染め上げたのと同じ力を枯れ野に映しているこの蟷螂はそれとはまったく異なる捉え方をしているのかも知れません。
そしてそう思う時、読者はこの句を通してやはりみずからに訪れつつある運命を見つめざるを得ないのではないでしょうか。
15日におうし座から数えて「目に映すべき課題」を意味する7番目のさそり座で新月を迎えていくあなたもまた、さながら掲句の「蟷螂」のごとく、らんらんとその目の内を燃えあがらせていくことになるはず。
ひとつの運命としての詩
「僕が、はじめてランボオに、出くはしたのは、二十三歳の春であつた。その時、僕は、神田をぶらぶら歩いてゐた、と書いてもよい。向うからやつて来た見知らぬ男が、いきんなり僕を叩きのめしたのである」
これは小林秀雄による有名な「ランボオ論」(1947年)の書き出しですが、なぜランボーはそれだけのインパクトと魅力を持ち得たのか。それは彼が作品だけでなく人間としても詩を生き切ったからでしょう。
19歳からのわずか3年で膨大な数の詩を書き上げた後、彼は詩を捨てて旅の商人となり、最後はアフリカの砂漠で生を終えたその鮮烈な生き様に、多くの人が詩の神髄を見たのだと思います。では、ランボー自身は詩やその使命についてどう考えていたのか。
間接的ではありますが、ある手紙の中で彼は「詩人は、その時代に、万人の魂のうちで目覚めつつある未知なものの量を、明らかにすることになるでしょう」と述べています。
運命を見つめるとは、あるいはこういうことを言うのかも知れません。それは寝ているうちに起きるというより、やはり小林のようにそれなりの衝撃を伴うものなのではないでしょうか。
今週のキーワード
未知はいつだって既知を叩きのめす