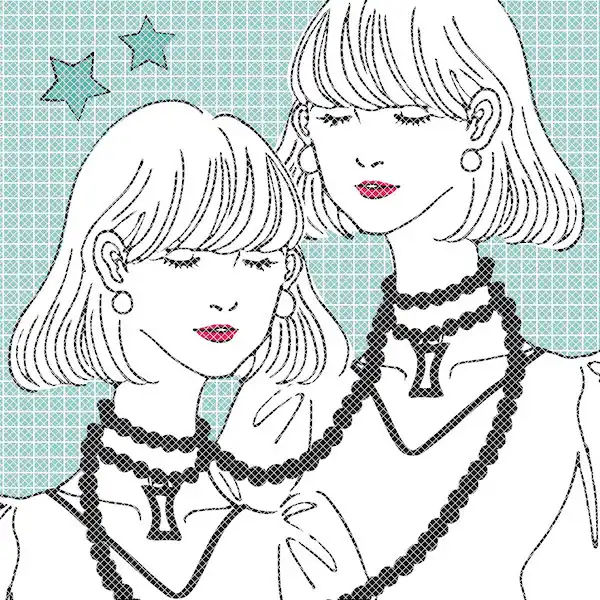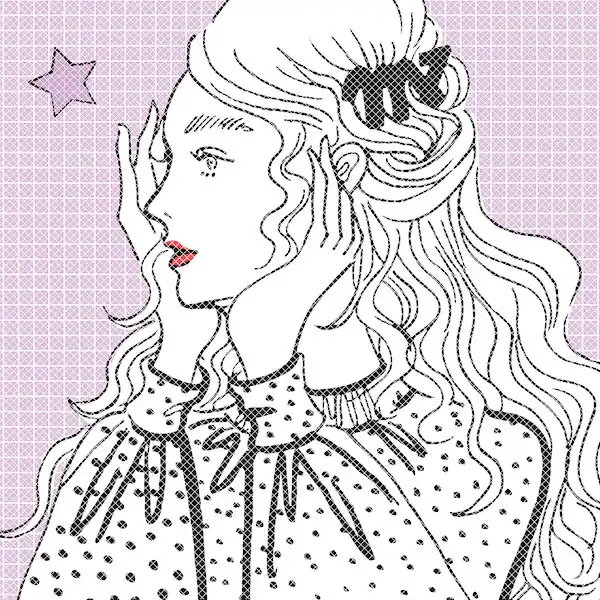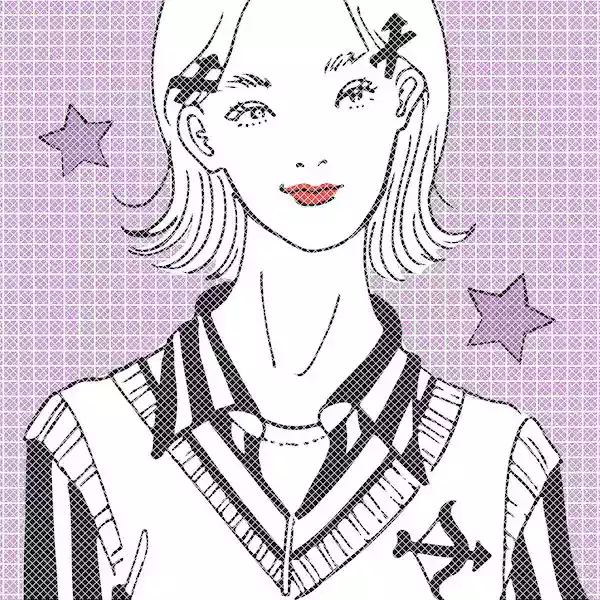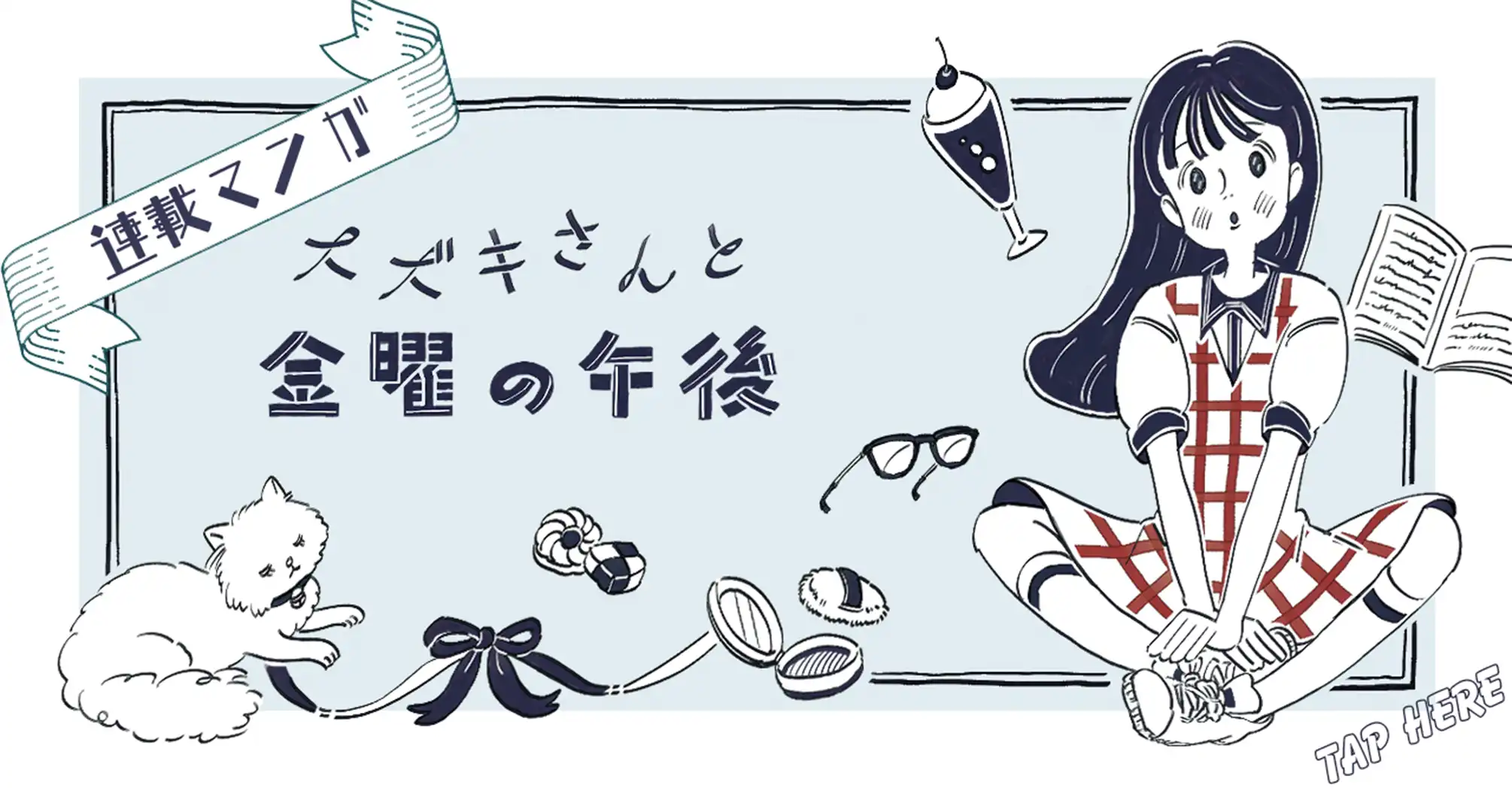さそり座
未知という不透明な経路をたどって

創造的なエクササイズ
今週のさそり座は、グリッサンの「不透明な言語」の実践のごとし。あるいは、創造的なエクササイズに取り組んでいくような星回り。
カリブ海フランス領マルティニック出身の作家、エドゥアール・グリッサンは、複数の言語の接触と衝突によって生じた言語的異種配合と多言語共存という自身のバックグラウンドに立った上で、自己表現という場においていかに引き受けつつそのジレンマを超えられるかという問題に触れて次のように述べました。
不透明性は、それ自体のなかに力を秘め隠しており、外的な根拠によって正当化されることがない。そしてそのことによって、不透明性は「透明性」という概念が私たちを疎外してしまうことに断固抵抗するための力を与えてくれる。私は、ハイチの亡命演劇集団クイドールによってマルティニックのフォール・ド・フランス市で上演された演劇のことを思い出す。言うまでもなく、劇の主要部分はハイチアン・クレオールで語られたため、私たちにその意味は分からなかった。しかしまさにこの不透明性ゆえに、私たちはそれがまぎれもなく「自分たちの」演劇であることを納得した。私たちはそのとき、未知という不透明な通路をたどって、理解に到達したのだ。
ここでいうクレオールとは、意思疎通ができない異なる言語圏の間で自然に作り上げられた言語のことを指しますが、グリッサンはそうして引き裂かれた言語のなかにこそ、言葉にふたたびポエティックな生命を与える力を見出し、その自覚的な使用を訴えかけたのです。
13日にさそり座から数えて「創造性の発露」を意味する5番目のうお座で新月を迎えていく今週のあなたもまた、誰か何かに「語られて」しまうのではなく自然なポエティックスとともに自ら「語る」行為のなかで、ある種の生まれ変わりを経験していくことができるはずです。
ポエティックスとしての旅と鎮魂
松尾芭蕉がその人生最後の旅について記した『おくのほそ道』が、単なるプライベートな旅日記ではなく、武家すなわち徳川家を呪詛の対象とし、国家を揺るがすほどの怨霊として恐れられていた「源義経の霊」の鎮魂を使命(ミッション)とする一種の「ヒーローズ・ジャーニー(英雄の旅)」を描いた一大叙事詩であったことはよく知られていますが、いくら旅慣れていた芭蕉としても、「そんなこと言われたって、どうやってやったらいいんだ」というのが本音だったのではないでしょうか。
ただ、彼には偉大なお手本がありました。平安末期から鎌倉時代に活躍した西行法師です。漂泊の吟遊詩人であった西行は、天皇家を呪詛の対象とする日本史上最強の怨霊とされる「崇徳院の霊」の鎮魂を命ぜられ、見事に使命を遂げていたのです。
とはいえ、芭蕉は今から300年前ほど前の人ですが、芭蕉の時代から数えて西行は500年前の人であり、私たちが想像する以上に遠い過去の人物だったはず。
いわば、訳の分からないうちに、見よう見まねで始めてみたというのが、『おくのほそ道』の実際だったのです。その意味で、芭蕉の『おくのほそ道』もまた、グリッサンの「不透明な言語」の実践の一つだったのだと言えるかもしれません。
今週のキーワード
見よう見まね