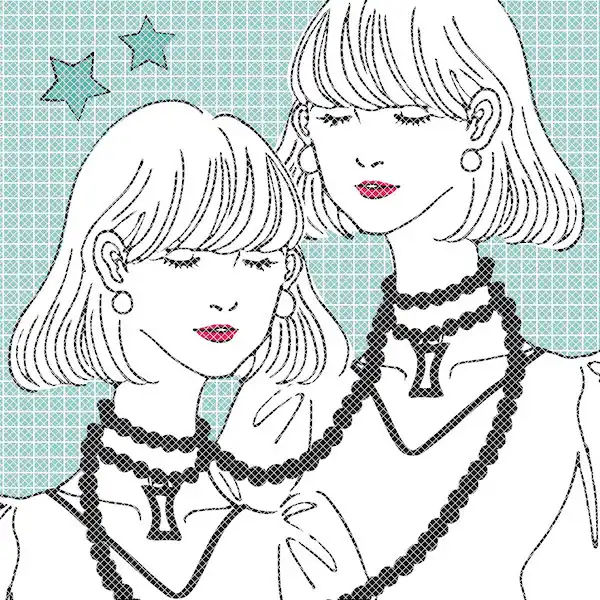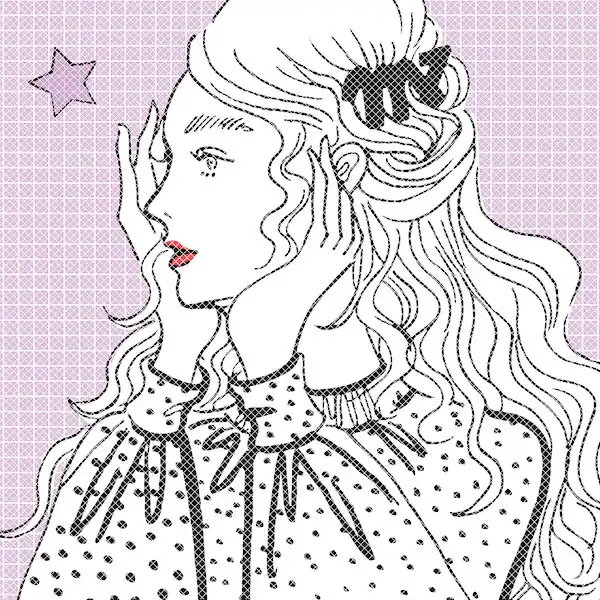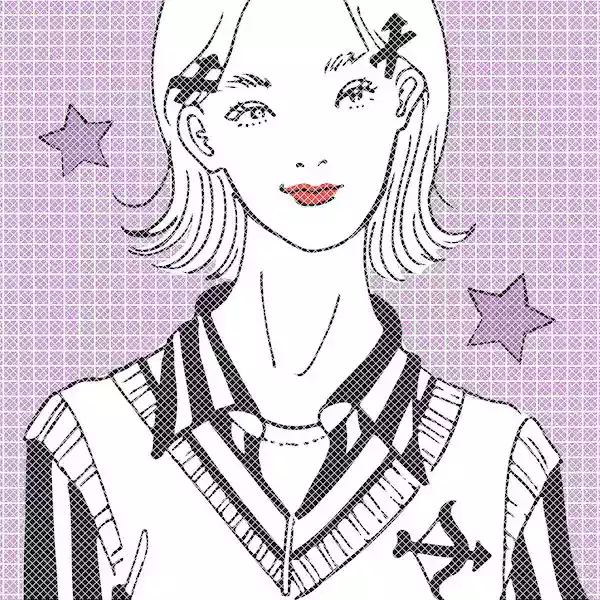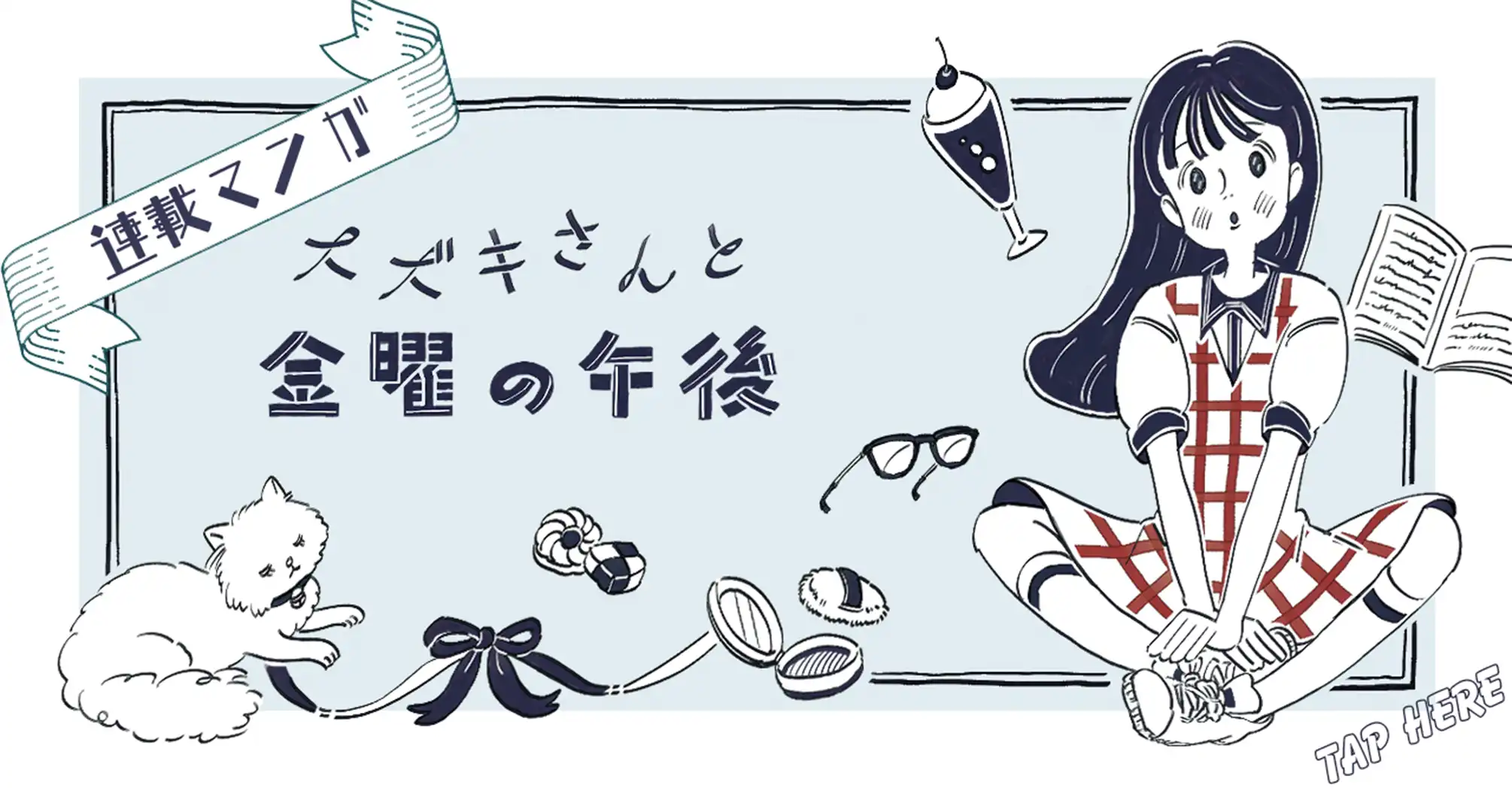やぎ座
スイッチを入れる

「俳句はなまの生活である」
今週のやぎ座は、『霜の墓抱き起こされしとき見たり』(石田波郷)という句のごとし。あるいは、どんな状況にあっても崇高さと雄々しさを忘れずに持っていこうと決意していこうとするような星回り。
作者は30歳の時に戦地で重度の結核にかかったことが転機となり、後半生は病中吟や療養句がテーマとなっていった俳人でしたが、掲句はおそらくその数年後、3度にわたる大手術をする直前に詠まれたものでしょう。全体が死への予感で貫かれています。
20代半ばで「俳句は文学ではないのだ。俳句はなまの生活である」(『鶴』1939年1月号)と気炎を吐いていた作者でしたから、ただ運命に流されるまま自己憐憫に浸っているようなタイプでは決してなかったはずですが、ここでは自分がまるで弱いものみたいになって「抱き起こされ」ています。つまり、ここに作者が目を背けることなく向きあうべき「なま」があり、それは作者にとって少なからずショッキングな事件だったはず。
しかも、そのときに偶然にも目に飛び込んできたのが、霜で凍りついたようになった墓だったと言うのです。文字通り、命あるものがことごとく死に絶えた氷の世界に手招きされたような心地がして、ぞっとしたのではないでしょうか。
ただし、と同時に作者の覚悟もここで決定的にきまったようにも思えます。どんなにおぞましい光景であっても、自分はこれからそれらを目に焼き付け、句に詠んでいくぞ、と。その意味で、1月21日にやぎ座から数えて「自己価値」を意味する2番目のみずがめ座へと冥王星が移っていく今週のあなたもまた、目をそむけることなく直視すべき「なま」の真実を見据えていきたところです。
生活に厳かさを
特にフリーランスの働き手にとって、「夜型にすべきか、朝型にすべきか」という問いはずっと頭のどこかにあって晴れてくれない永遠のテーマと言えますが、黒人女性で初めてノーベル文学賞をとったトニ・モリスンの場合、自分の作品の執筆にとりかかる時間帯は時代によって変わっていきました。
1970年代から80年代にかけてのインタビューでは、夜に小説を書くと答えているものの、90年代に入ると早朝になったのですが、その理由が「日が暮れるとあまり頭がまわらなくて、いいアイデアも思いつかない」からだと言います。
執筆のために5時ごろ起床、コーヒーを作って「日の光が差してくるのを眺める」のが毎日の儀式であり、特に日光の部分は重要なのだとか。
作家はみな工夫して、自分がつながりたい場所へ近づこうとする。(中略)私の場合、太陽の光がそのプロセスの開始のシグナルなの。その光のなかにいることじゃなくて、光が届く前にそこにいること。それでスイッチが入るの。ある意味でね(メイソン・カリー『天才たちの日課―クリエイティブな人々の必ずしもクリエイティブでない日々―』)
今週のやぎ座もまた、自分なりの仕方で「自分がつながりたい場所へ近づ」いていくべく工夫を凝らしていくことが一つのテーマとなっていくでしょう。
やぎ座の今週のキーワード
「なま」と向きあうための儀式