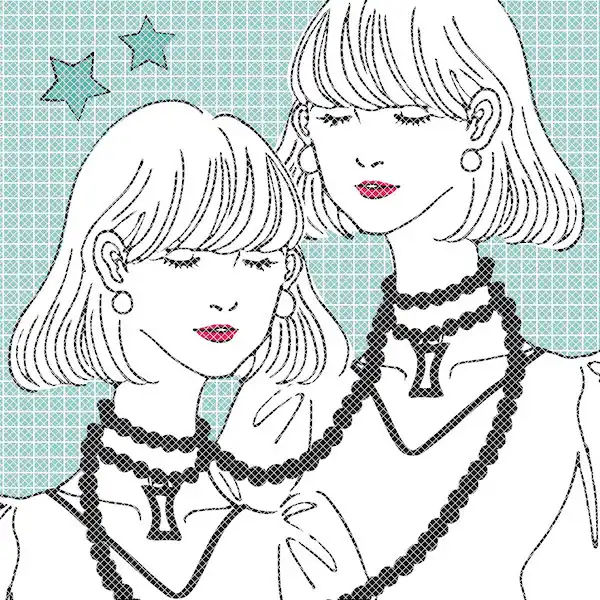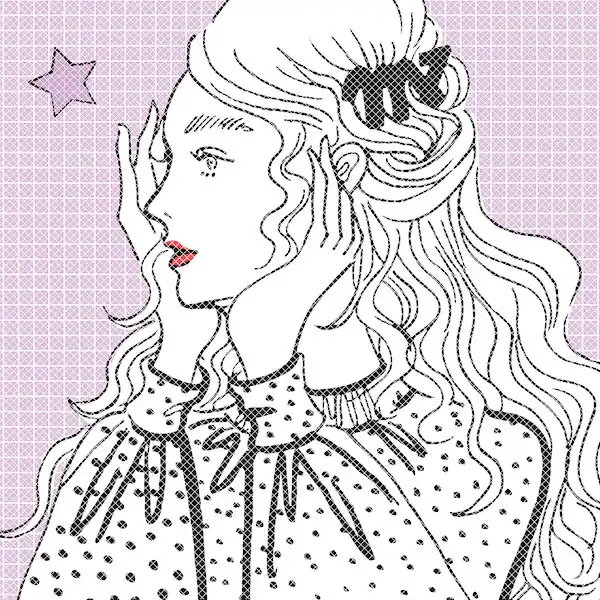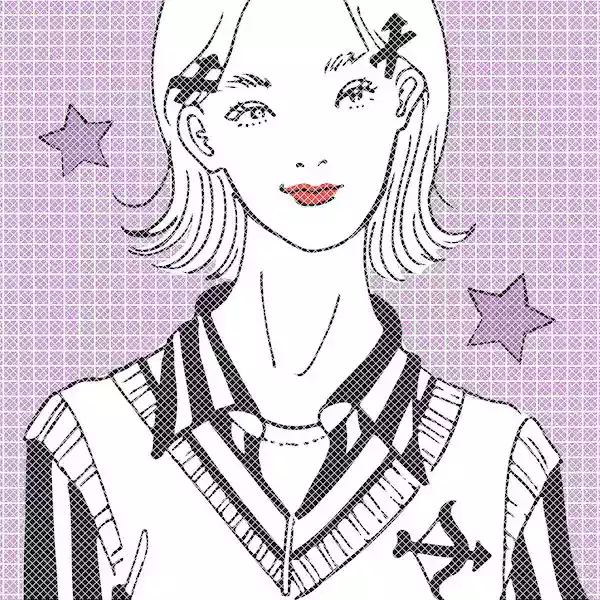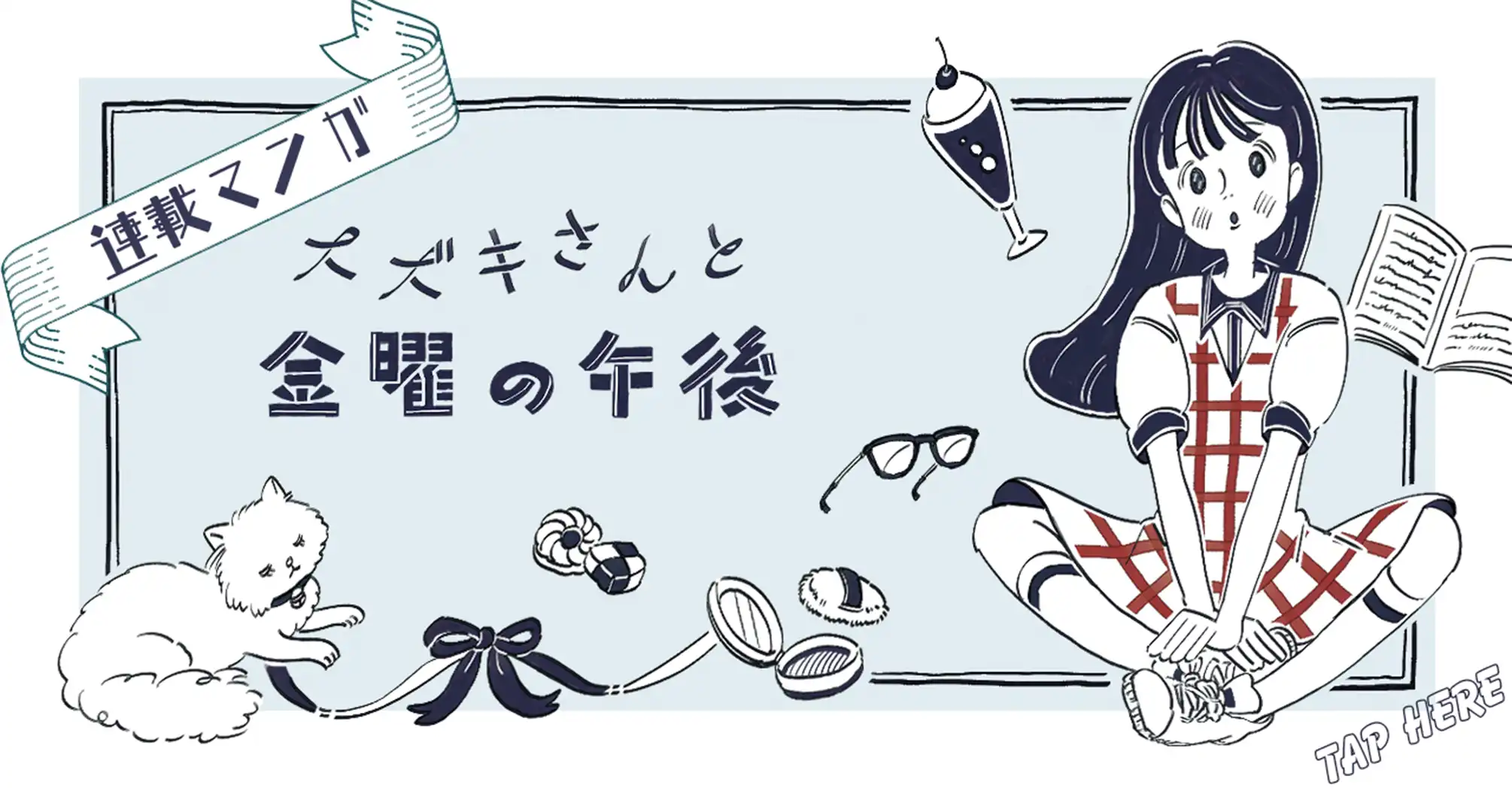やぎ座
「わたし」の喪失と再発見

流れよ涙、雨のごとく
今週のやぎ座は、『病み呆けて泣けば卯の花腐しかな』(石橋秀野)という句のごとし。あるいは、自身を空っぽの器にしていこうとするような星回り。
「卯の花腐(くた)し」は初夏の季語で、卯の花を腐らせるほどにしとしとと降り続く雨、という意味。
わずか38歳で生涯を閉じた作者は、文芸評論家として名高い山本健吉の妻であったと同時に、ひとりの女流俳人でもありました。「病み呆けて」とあるように、掲句もまた、長患いのすえにすっかり痩せ衰えてしまっていること暗に示した病床句のひとつ。
ふと病人は、来し方のことどもを思い、また行く末を思い、自分の死や、残された夫やまだ幼い娘のことを思って、いつの間にか涙が溢れていたのでしょう。
そうして、一体いつまでも降り続くのかと呆れるほどの雨に、おのずとついいましがた自身の身に起きていることを重ねたのです。そしておそらく、こうして自分自身を出し切った仕事ができるかどうかこそが、俳人として自身の腕を昇華させていけるかを大きく左右していくはず。
その意味で、14日にやぎ座から数えて「カタルシス」を意味する12番目のいて座で満月を迎えていく今週のあなたもまた、中途半端に我慢したり残留させてしまうよりも、いっそどこかで思いをいったん出し切るくらいのつもりで過ごしていくといいでしょう。
予感を確信に変える
忍び寄る死や病いが詩人を成長させる例は枚挙に暇がありませんが、一方で一般的には、失明すれば文字も読めなくなり、創作活動も難しくなると考えられがちであるにも関わらず、実際に著名な詩人などを見ていくと、逆の例が多くあることにも気づかされます。
例えば、イングランドの大詩人ミルトンは、44歳で過労のために失明した後、50歳で代表作となった一大叙事詩『失楽園』の制作に着手して9年後に刊行しましたが、その他の詩人としての業績もほとんどすべてが失明後に書かれたものでした。
もちろん、ホメロスのような描写がきわめて視覚的な詩人というのも多い一方で(ただ彼はその伝説において盲人だった)、聴覚的で音楽的であることは詩の本分であり、ボルヘスによれば視覚的でない詩人こそが「真に知的な詩人」なのだと言います。
ミルトンの失明は自発的なものでした。彼には自分が大詩人になる予感があり、失明したことでそれが確信に変わったのです。ミルトンがソネットにおいて自分の盲目について語っている箇所では、「in this dark world and wide(この暗く広い世界に)」とありますが、今週のやぎ座もまたそうした“一線の踏み越え”ということがテーマとなっていきそうです。
やぎ座の今週のキーワード
in this dark world and wide(この暗く広い世界に)