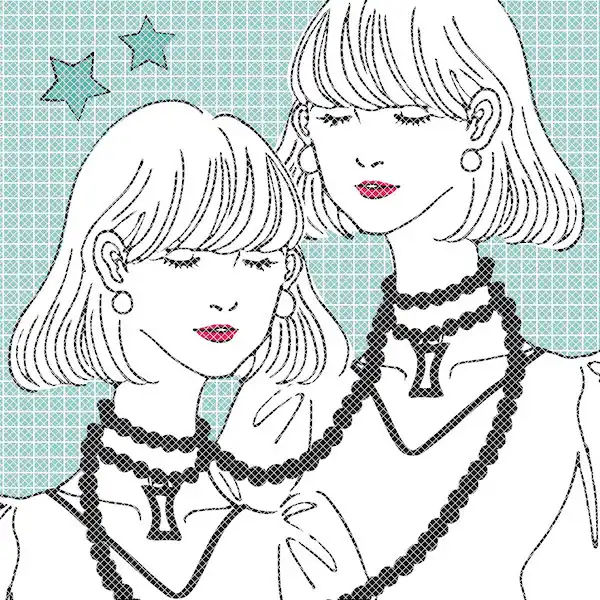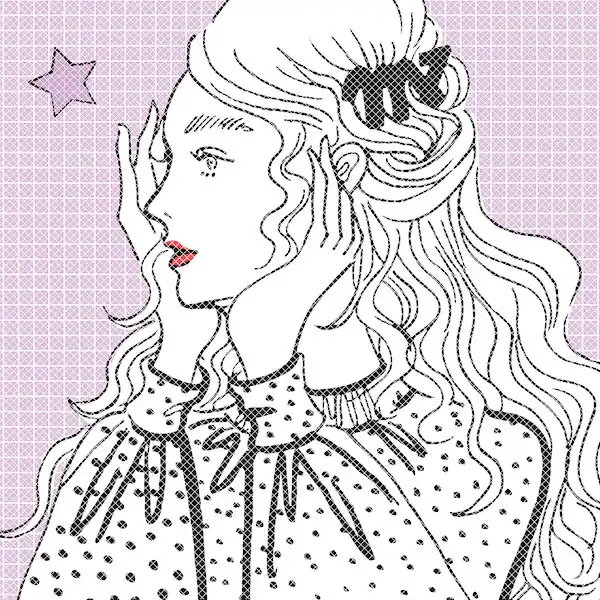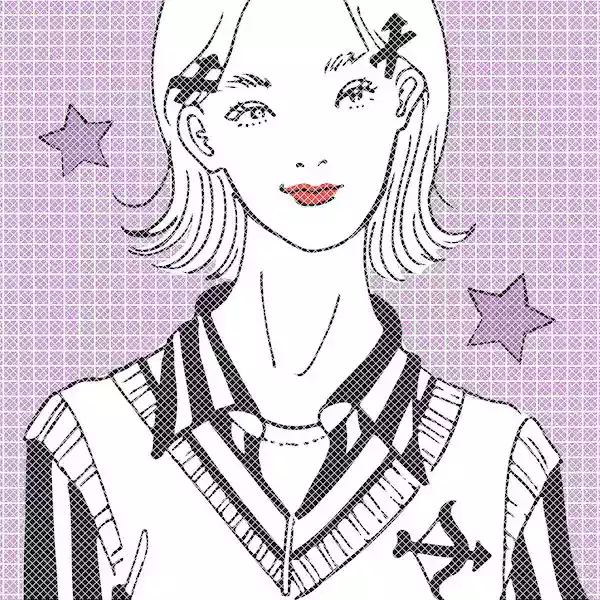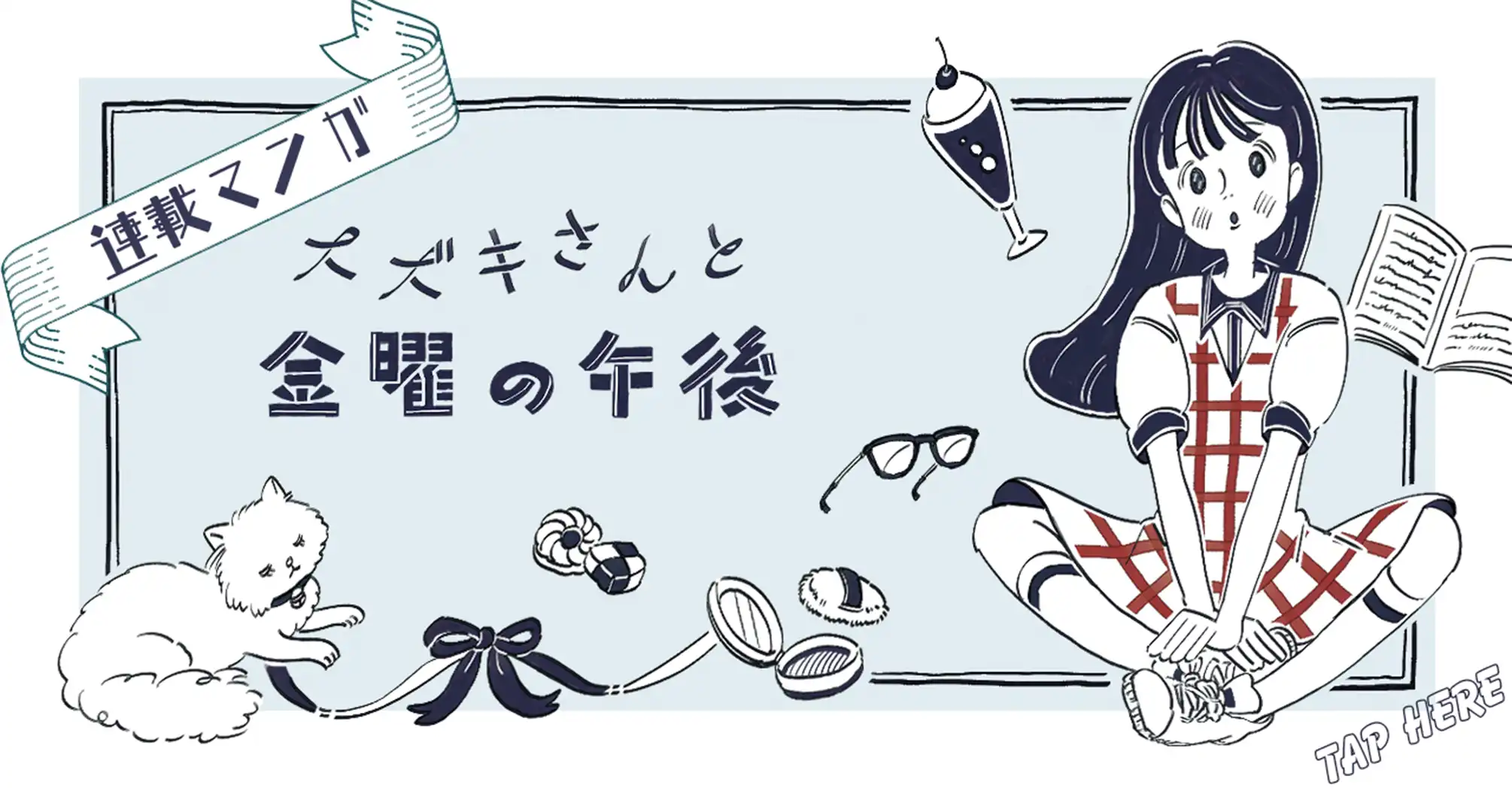おひつじ座
おのれを円で囲む

夜の世界は丸い
今週のおひつじ座は、『灰皿を持ちて夜長に加りぬ』(後藤比奈夫)という句のごとし。あるいは、フーっと深く、長く息を吐き出していくような星回り。
秋分を過ぎると、朝夕の空気の涼しさはいよいよ増して、夜もグッと長くなったように感じられてきます。そんな「夜長」の静かな時間を味わうため、作者はおそらく洗った灰皿を手に書斎へ向かったのでしょう。
そうして、万物に帯びる静かな影へと加わって、みずからもその深みへ溶け込んでいく。書斎で行おうとしているのが読書であれ書きものであれ、単なる喫煙であれ、それらはあくまで夜長に加わるための手段に過ぎず、夜の長さを豊かさとして感じ取っていくための一種の儀式のようなものなのだとも言えるかも知れません。
ここで、かつて文化人類学者のクロード・レヴィ=ストロースが、インタビューの中で受けた「さまざまな神話をどう結びつけているのか」という問いかけへの答えの一節を引用しておきたいと思います。
経路はどうでもいいのです。すべてが相互に関連しあっており、神話の世界は丸いことがわかっている以上、ある道をとっても別の道を選んでもいいのです。結局はいつも自分の家に帰り着くのですから。
10月6日におひつじ座から数えて「家」を意味する4番目のかに座で下弦の月を迎えていく今週のあなたもまた、改めて自分なりの儀式次第を工夫してみるといいでしょう。
服の起源
書家・書道史家の石川九楊は、衣類のはじめは腰にまわした一本の紐だったという観点から、次のように述べています。
腰紐や帯、ベルトを結ぶことによって、自己の輪郭を定め、自己をここまでと規定するに至ったところに、紐衣=腰紐の起源はたどれる。その名残りが、日本の神社に残る注連をまわした巨木である。それは樹木に衣類を着せているのだ。腰紐=注連――それは自己と他者を区切ることであった(『失われた書を求めて』)
相撲の土俵などもそうですが、注連縄などの紐で囲まれたところには自然と神聖感が生じます。円で囲むことで、象徴的にその中を眼に見えなくさせる効果をもたらしている訳ですが、こうした象徴的行為が古代において頻繁に行われていたことは、祭祀に使った祭器などが人の目に触れないよう地中に埋められたことなどと同じ発想であり、ある程度納得がいくことでしょう。
とはいえ、人が衣服をまとうようになった理由もまた、そうしたある種の「結界観念」にあるというのは驚くべき指摘と言えます。これはすなわち、人の目から隠すことによって初めて物事は神聖さを得るのであり、それは自己にもそのまま適用できるということ。
逆に言えば、これが自分でございと、そのまま包み隠さずでんと置かれた自己というのは、自己未満の何かなのです。その意味で、今週のおひつじ座もまた、自分が何か大切で尊い存在であるという実感を得るためには、改めて何でおのれを包み、いかに紐で囲んでいくべきかがテーマとなっていきそうです。
おひつじ座の今週のキーワード
漏らしてはいけない秘密の発生源であり、恐ろしい中心としての自分